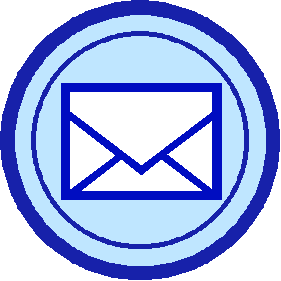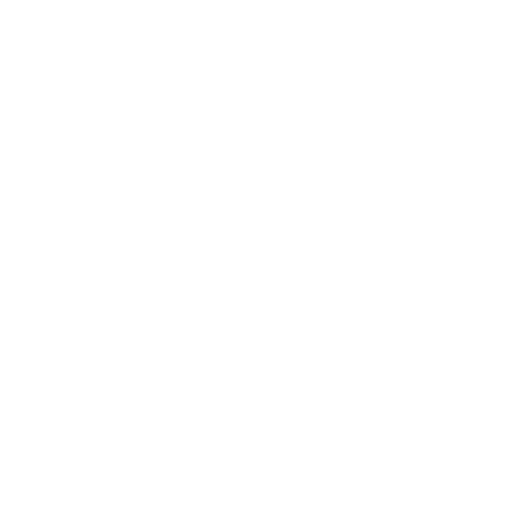算定表上限2000万円超過年収の義務者養育費を算定した家裁審判紹介
○申立人父は、相手方母との間で子A・Bに対し、1人当たり月額20万円の養育費を支払うと定めて離婚しましたが、その後、再婚し再婚相手の子E・Fと養子縁組し、更に再婚相手との間に実子Gが生まれたことで、A・Bの養育費減額調停を出して不調に終わっていました。審判は東京・大阪養育費等研究会が提唱する算定方式によれば、A・Bの養育費は月額15万円が相当としました。
○しかし、「(申立人の収入が)これだけ高額であれば、申立人が調停での合意内容を維持するべく、申立人の生活費を少なくして養育費に充てることは可能なはずである。いったん調停で合意をして養育費を決めた申立人が、これらの努力をしさえすれば、前記算定方式により算定された1人当たり月額約15万円と調停で合意された1人当たり月額20万円との差額を補うことは可能であると思われる」として、月額20万円を維持しました。
**********************************************
主 文
一 本件申立てを却下する。
二 手続費用は各自の負担とする。
理 由
第一 申立ての趣旨
申立人は、相手方に対し、A及びBの養育費として、1人当たり月額11万2494円を支払う(申立人は、調停申立ての際、相当額に減額することを求めたが、審問において1人当たり月額11万2494円を支払うことを求める旨述べた。これに対して、相手方は、減額せずに1人当たり月額20万円が支払われるべきであるという。)。
第二 当裁判所の判断
一 認定事実
一件記録によれば、次の事実が認められる。
(1)申立人(昭和40年×月×日生)と相手方(昭和42年×月×日生)は、平成10年×月×日婚姻し、両者の間にA(平成11年×月×日生)及びB(平成14年×月×日生)が生まれた。
(2)申立人と相手方は、平成20年×月×日、A及びBの親権者をいずれも相手方とし、申立人が相手方に対して、A及びBの養育費として、平成20年×月からA及びBがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、1人当たり月額20万円を支払う旨定めて、調停離婚した(熊本家庭裁判所平成19年(家イ)第××号夫婦関係調整調停事件)。申立人は、現在、この調停の合意内容のとおり、1人当たり月額20万円の養育費を支払っている。
(3)相手方は、平成21年×月×日、Cと婚姻し、現在、同人、A及びBと同居して、A及びBを監護養育している。
(4)申立人は、平成22年×月×日、Dと婚姻し、同日、同人の子であるE(平成11年×月×日生)及びF(平成13年×月×日生)と養子縁組をした。また、Dとの間にG(平成24年×月×日生)が生まれた。申立人は、現在、D、E、F及びGと同居して、E、F及びGを監護養育している。
(5)申立人は、医師の資格を有し、医療法人の代表者として働いており、平成24年分の総収入額は6171万6840円であった(=給与収入額6155万3230円+雑所得額16万3610円。この金額は社会保険料が控除される前のものである。)。
申立人の妻Dは、申立人住所地を本店所在地とし、かつ、申立人が代表者となっている医療法人の事業に関連する事業を行っている株式会社の経営者として働いており、平成24年分の総収入額は330万円であった。
相手方は、薬剤師の資格を有し、薬局の経営者として働いており、平成24年分の総収入額は999万3504円であった(=給与収入額960万円+不動産所得額39万3504円。この金額は社会保険料が控除される前のものである。)。相手方の夫Cは、相手方経営の薬局で働いており、平成24年分の総収入額は240万円であった。なお、雑所得額や不動産所得額について、公租公課、職業費及び特別経費を控除する対象として総収入額に含めることに疑義はあるが、本件では給与収入額と比較して少額なので、上記のとおり総収入額に算入するのが相当である。
(6)申立人は、相手方に対し、平成25年×月×日、前記(2)記載のとおりの養育費を相当額に減額して支払うとの調停を申し立てたが(熊本家庭裁判所平成25年(家イ)第××号、第××号)、同年×月×日、調停不成立となって本件審判手続に移行した。
二 申立人が負担すべき養育費の標準的な金額及び民法880条該当性について
(1)申立人が負担すべき養育費の標準的な金額については、東京・大阪養育費等研究会が提唱する算定方式(判例タイムズ1111号285頁参照、以下、同文献については、頁数のみで示す。)を採用して算定するのが相当である。これにより、権利者及び義務者の総収入額や未成年者の人数、年齢を考慮して一応の養育費の金額を算定し、特段の事情があれば、修正を加えて算定することになる。
(2)これを本件についてみると、申立人の平成24年分の総収入額6171万6840円に基礎収入割合0・27を乗じると基礎収入額は、1666万3547円となる(=6171万6840円×0・27、1円未満は四捨五入した。以下同じ)。申立人の妻Dの平成24年分の総収入額330万円に基礎収入割合0・40を乗じると基礎収入額は、132万円となる(=330万円×0・40)。相手方の平成24年分の総収入額999万3504円に基礎収入割合0・36を乗じると基礎収入額は、359万7661円となる(=999万3504円×0・36)。相手方の夫Cの平成24年分の総収入額240万円に基礎収入割合0・42を乗じると基礎収入額は、100万8000円となる(=240万円×0・42)。
なお、相手方は、申立人や相手方を自営業者として算定すべきであると主張するが、自営業者の総収入額に当たる「課税される所得金額」は、既に給与所得者の職業費に該当する費用及び社会保険料が控除されているから、前記算定方式では、自営業者と給与所得者の基礎収入割合が異なるとされているところ(289頁*11参照)、申立人と相手方の総収入額は社会保険料の控除前のものであり、資料によると、給与収入額が記載されている市県民税所得証明書においては、職業費も控除されていないので、申立人及び相手方を給与所得者として算定するのが相当である。そして、申立人のような高額所得者については、基礎収入割合をいくらにすべきか問題となるが、高額所得者の場合、貯蓄や資産形成に回る部分が大きくなり、その全てが生活に消費されるわけではないことや申立人の主張(計算根拠)を考慮して、基礎収入割合を0・27とした(松本哲泓「婚姻費用分担事件の審理-手続と裁判例の検討」家庭裁判月報62巻11号77頁参照)。また、相手方は、その夫Cが前妻との間の子の養育費として月額9万9000円を支払っているので、総収入額から控除するべきである、申立人の妻が前夫から養育費を受給している場合には、総収入額に含めるべきである旨主張するが、いずれもこれらを裏付けるに足りる資料はないので考慮しない。
次に、A及びBの生活費を算定する。申立人及びその妻Dの基礎収入額の合計は、1798万3547円であり(=1666万3547円+132万円)、この金額から申立人、その妻D、E、F、G、そしてAとBの生活費が賄われるところ、AとBの生活費に充てられる金額は、460万0443円となる(=1798万3547円×(55+55)÷(100+55+55+55+55+55+55))。なお、申立人及びその妻Dの基礎収入額を合計すると、A及びBを養育する義務のないDがA及びBの生活費の一部を負担することになるが、Dの収入は、申立人住所地を本店所在地とし、かつ、申立人が代表者となっている医療法人の事業に関連する事業を行っている株式会社からのものであること、申立人の基礎収入額と比較してDのそれが少ないことから、申立人及びその妻Dの基礎収入額を合計するのが相当である(岡健太郎「養育費・婚姻費用算定表の運用上の諸問題」判例タイムズ1209号八頁参照)。申立人は、Dの生活費指数を55ではなく、100とすべきであると主張するが、Dは、申立人と同居しており、住居費の負担がないのであるから55とするのが相当である(291頁注二参照)。
申立人の養育費負担額は、AとBの生活費460万0443円を申立人側(申立人及びその妻D)と相手方側(相手方及びその夫C)の基礎収入額で按分すべきであるから、366万2468円となる(=AとBの生活費460万0443円×申立人とその妻Dの基礎収入額の合計1798万3547円÷(1798万3547円+相手方の基礎収入額359万7661円+相手方の夫Cの基礎収入額100万8000円))。ここでは、相手方及びその夫Cの基礎収入額を合計しているが、Cが相手方経営の薬局で働いており、かつ、その金額が相手方の基礎収入額と比較して少ないことから両者を合計するのが相当である。
以上により、前記算定方式によると、A及びBの1人当たりの養育費は、月額15万2603円となる(=366万2468円÷2人÷12か月)。
(3)民法880条該当性について
本件養育費減額申立ては、申立人と相手方との間で養育費を1人当たり月額20万円とする調停が成立していることを前提としているから、減額が認められるためには、まず「事情に変更を生じた」(民法880条)といえる場合でなければならない。この点、同調停成立時には、申立人が生活保持義務を負う対象としてAとBの2人がいただけであるが、現在では、同義務の対象として妻Dがいる他、養育すべき子が合計5人いるのであるから、「事情に変更を生じた」というべきである。もっとも、民法880条は「事情に変更を生じた」場合には直ちに協議内容を変更しなければならないとするものではなく、変更を「することができる。」としているのであるから、変更することが相当かどうかを検討する。
申立人は、1人当たり20万円の養育費を支払う旨の調停を成立させたにもかかわらず、その意思に基づいて、調停成立後約1年2か月で再婚及び養子縁組をし、約3年後に子をもうけた。予期しない収入の減少というのであればともかく、自らこのような状況を作り出すことにより、いったん成立した調停の効力を覆すのを認めることには慎重であるべきといえる。
また、申立人が6年制の大学教育を受けた医師であり、しかも多額の収入があることからすると、AとBが少なくとも4年制の大学教育を受け終わるまで養育費が支払われるのが相当であるにもかかわらず、養育費を定めた調停においてそのような合意がなされなかったのは、毎月の養育費の金額が高額であり、養育費支払の終期である満20歳に達する日の属する月から4年制の大学卒業時までは既に支払われた毎月の養育費の一部を充てることを予定していたからであるというべきである。それにもかかわらず、同じ終期のままで養育費の月額だけを減額することには慎重であるべきといえる。
さらに、申立人の基礎収入額を算出する際に検討したとおり(前記二(2)),高額所得者の場合、収入が貯蓄や資産形成に回る部分が大きくなり、その全てが生活に消費されるわけではないことを考慮して、基礎収入割合を0・27と相当低くしたのであるから、申立人が調停での合意内容を維持するべく、貯蓄や資産形成に回る部分を少なくして養育費に充てることは可能なはずである。申立人自身の生活費について、前記二(2)においてA及びBの生活費を算定したのと同様に考えると、年額418万2218円(月額34万8518円)となるが(=申立人及びその妻Dを併せた基礎収入額1798万3547円×100÷(100+55+55+55+55+55+55))、これだけ高額であれば、申立人が調停での合意内容を維持するべく、申立人の生活費を少なくして養育費に充てることは可能なはずである。
いったん調停で合意をして養育費を決めた申立人が、これらの努力をしさえすれば、前記算定方式により算定された1人当たり月額約15万円と調停で合意された1人当たり月額20万円との差額を補うことは可能であると思われるのに、これらの努力をせずに直ちに減額することを認めるのは相当ではない。したがって、本件では「事情に変更を生じた」(民法880条)とはいえるが、調停で合意された1人当たり20万円という養育費は減額しないこととする。
三 以上からすると、申立人の相手方に対する養育費減額の請求は認められない。よって、本件申立ては理由がないから却下することとし、主文のとおり審判する。