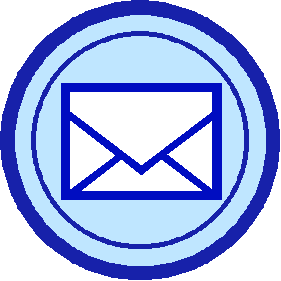離婚後再婚養子縁組で実親養育料支払義務免除を認めた家裁審判紹介
○この記載の根拠となる判例を掲示していませんでしたが、養子縁組の制度は未成年子の保護養育を主たる目的とし、縁組は子の福祉と利益のためになされなければならないものであり、未成年子との養子縁組には子の養育を、扶養をも含めて全面的に引受けるという合意が含まれているものと解され、養親の資力の点から右養親において充分に扶養の義務を履行できない場合を除いては、実親の扶養義務は順位において、養親のそれに後れるものと解すべきであるとした昭和46年11月11日札幌家裁小樽支部審判(判タ289号399頁)全文を紹介します。
○私は、再婚しても連れ子と養子縁組をしない場合でも、事実上の養親であり、事実上の養親が第一次的養育義務を負うと考えていますが、養子縁組をしなければ養育義務は無いとの考えもあるようです。この考えを否認した裁判例を探して紹介したいと思っています。
*********************************************
主 文
申立人と相手方間の札幌家庭裁判所昭和44年(家イ)第977号夫婦関係調整調停事件調停調書調停条項第4項を取消す。
理 由
申立人は、主文掲記の調停条項につき昭和46年7月以降の養育料債務の免除を求める旨の調停を申立て、その申立の実情は、申立人と相手方は昭和44年11月21日札幌家庭裁判所において調停離婚し、その調停条項第2項として、当事者間の長女A(昭和40年3月28日生)の親権者を相手方と定める、同第4項として、申立人は相手方に対しAの養育料として昭和44年12月からAが中学校を卒業する月まで毎月10日限り1ケ月8000円宛を支払う旨の合意が成立したものであるが、相手方は昭和46年2月22日B(昭和13年10月3日生)と婚姻届出をし、同日Aは相手方を代諾権者としてBと養子縁組をしたから、申立人の上記養育料債務の昭和46年7月分以降の免除を得たいというにある。
本調停は昭和46年7月2日申立があり、同年8月18日から9月8日まで調停が行われたが不成立となり審判に移行したものである。
調査の結果によれば、上記申立の実情のとおりの事実が認められるほか、相手方は離婚後引き続きAを監護養育してきたもので、Aの養子縁組について申立人には何らの交渉もなかつたこと、相手方の夫Bは○○自衛隊に勤務し手取月収額は約6万円であり、養女であるAを扶養する余力は十分であることが認められる。
そこで養親と実親との未成熟子に対する扶養義務の順位について考えるに、一般に民法上扶養義務の順位については明文の規定が存しないが、現在の養子制度は未成年子の保護養育を主たる目的とし、縁組は子の福祉と利益のためになされなければならないものであり、未成年子との養子縁組には子の養育を、扶養をも含めて全面的に引受けるという合意が含まれているものと解される。換言すれば養子縁組には親子の愛情による結合と親の愛情をもつて監護養育の実質が伴わなければならないものであり、縁組には養親がかような結合と実質を伴つた親としての役割を果すという合意が含まれているものと解される。
従つて実親との関係は扶養をも含めて一定の範囲で制限されるものと考えることができ、養親が資力がない等の理由によつて充分に扶養の義務を履行できない場合を除いては、実親の扶養義務は順位において養親のそれに後れるものと解すべきである。即ち、養子の養親と同程度ではあるが、次順位で扶養義務を負うものと解すべきである。そしてこの理は本件のように実父母離婚後未成年子の親権者となつた一方が後に再婚しその配偶者がその未成年子と縁組した場合にも異るところはないものと解すべきである。
即ち、この場合には家庭裁判所の許可を要せずして養子縁組をすることができるのであるが、この点については、未成年子の許可制度が未成年子の保護に重点をおくものであるという点から考えるならば制度全体としては徹底しないものであるといえる一方逆に許可を必要としないものとしても未成年子の保護は全うされる筈であるという前提がおかれていると理解することもできるのであつて、この場合に法が許可を要しないとしていることは、養親の扶養義務が実親のそれに順位において先んずるという前示の解釈を支持するものでこそあれ、これを否定する理由ではあり得ず、ほかに解釈を異にする根拠は見出し難い。
実父母離婚後未成年子の親権者となつた一方が、再婚しないままその未成年子を他にいわゆる養子に出した場合を想定するならば、この場合に同一の理が貫かれるべきことは当然であるとともに、その一方が再婚し、その配偶者が未成年子と養子縁組した場合にはなお一層未成年子の保護は全うされることが期待されるのであるからこの場合に親権者とならなかつた実親の他方の扶養義務が後退すると考えることは一層容易であるということができる。
のみならず前示認定事実にもみられるとおり、本件のような場合には、未成年子の親権者とならなかつた実親の他方は、その未成年子の養子縁組についてはその意思を問われないのが通常であると考えられるし、また養子縁組をした再婚配偶者としては一般に税法上の利益等をもうけるのであり、これらの事情は派生的、受働的なものではあるけれども前示の解釈を肯定すべき根拠とすることができるものといえる。
また未成年子の養子縁組の意思、とくに養親たるべき者の意思が、その未成年子の実親からの扶養料の有無、多少によつて左右されるようなことがもしあるとすれば、そのことは一般に結局親子の愛情による結合と親の愛情をもつてする監護養育の実質の実現を損うことに通ずるものと考えられるのであり、この点からしても実親からの扶養は第二次的なもの、例外的なものとするのが妥当であるといわなければならない。
そうすると申立人のAに対する扶養義務は相手方の配偶者であるBがAと養子縁組をした後は、B及び相手方の同女に対する扶養義務に順位において後れるものとなつたのであるから、主文掲記の調停事件調停調書調停条項第4項はこれを取消すべきものである。しかしてこの取消は遡及効を有するものと解されるが、養子縁組後の養育料について申立人は昭和46年7月分以降の義務の免除を申立てるのみで、同月分以降は未履行となつているから同条項を取消すのみにとどめることとする。
よつて主文のとおり審判する。(家事審判官 広岡得一郎)