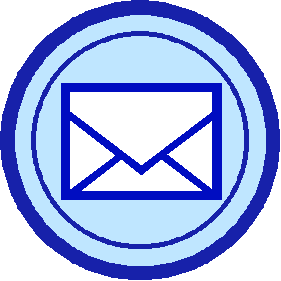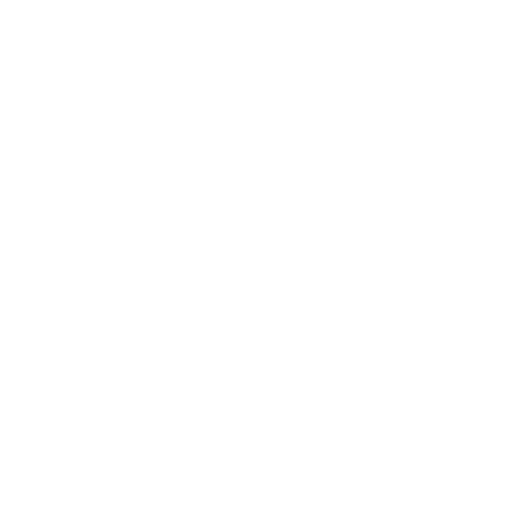中国人妻から日本人夫への養育費請求を日本での算定方法認めた家裁審判紹介
○その判決において、長男である未成年者は申立人が扶養し、長女は相手方が扶養するものと定められ、養育費は、各扶養者が自ら負担すると定められたため、相手方は、長女を引き取ったところ、申立人が、相手方に対し、未成年者の養育費の支払を求める調停を申し立て、同調停は不成立となり、本件審判手続に移行し、相手方が、申立人に対し、未成年者の養育費として相当額を支払うことを求めました。
○この事案で、当該判決において、養育費は、各扶養者が自ら負担するものと判断されたから、未成年者については、申立人が負担することとなるが、中国婚姻法37条に基づくと、「子女が必要な時」であれば、申立人は、相手方に対し、必要な生活費及び教育費の負担を求めることは可能であると解され、申立人妻は現在も職に就いていない状態である一方、相手方夫は約1041万円の給与収入を得ていることからすれば、本件において、申立人は、相手方に対し、準拠法である中国法において法的効力が認められている最高人民法院による司法解釈に関する意見書に基づいて養育費を算定することは相当でなく、日本における算定方法を参考として、未成年者の養育費の請求をすることができるというべきであるとて養育費の相当額を算定し、令和2年8月から令和4年3月までの養育費の合計額は、200万円(10万円×20か月)となり、相手方は、申立人に対し、同額を直ちに支払うべきであり、また、相手方は、申立人に対し、未成年者の養育費として、令和4年4月から、未成年者が満18歳に達する日の属する月まで、月額10万円を支払うべきであるとして支払を命じた令和4年4月28日横浜家裁小田原支部審判(判タ1526号123頁)全文を紹介します。
○日本人夫が抗告しており、その結果は別コンテンツで紹介します。
*********************************************
主 文
1 相手方は,申立人に対し,200万円を支払え。
2 相手方は,申立人に対し,令和4年4月から,未成年者が満18歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,月額10万円を支払え。
3 手続費用は各自の負担とする。
理 由
第1 申立ての趣旨
相手方は,申立人に対し,未成年者の養育費として相当額を支払え。
第2 当裁判所の判断
1 認定事実
一件記録によれば,以下の事実が認められる。
(1)申立人(1984年*月生)と相手方(1978年*月生)は,2008年(平成20年)9月8日に中華人民共和国駐日本国大使館において婚姻の登記をし,日本で生活をしていたが,次第に関係が悪化し,申立人は,2015年(平成27年)10月,当事者間の2人の子(本件事件の未成年者である長男(2011年*月*日生)及び長女(2014年*月*日生))を連れて中国へ帰国し,相手方と別居した。
(2)申立人と相手方に対しては,2017年(平成29年)11月30日,中国において,離婚判決がなされた。判決において,長男である未成年者は申立人が扶養し、長女は相手方が扶養するものと定められ,養育費は,各扶養者が自ら負担すると定められた。相手方は,令和元年5月,長女を引き取った。(住民票上は令和元年9月24日転入)
(3)申立人は,令和2年8月27日,相手方に対し,未成年者の養育費の支払を求める調停を申し立てたが(横浜家庭裁判所小田原支部令和*年(家イ)第*号),同調停は,令和3年10月22日,不成立となり,本件審判手続に移行した。
(4)申立人は,就業していたが失業し,平成31年1月から令和2年12月まで,稼働収入は0円であり(添付資料2,3),現在も職に就いていない。
(5)相手方の収入は,令和2年において約1041万円である(令和3年12月6日発行の課税証明書)。
2 国際裁判管轄及び準拠法
(1)国際裁判管轄
本件は,中国に居住する申立人(元妻)が,日本に住所を有する相手方(元夫)に対し,妻が扶養する旨定められた当事者間の長男である未成年者の養育費の支払を求める事案である。国際裁判管轄については,家事事件手続法3条の10が適用され,同条によれば,同条に規定する扶養義務者であって申立人でないものの住所が日本国内にあるときに該当するから,日本の裁判所が管轄権を有することになる。
(2)準拠法
扶養義務の準拠法に関する法律2条1項によれば,扶養権利者の常居所地法によるところ,申立人の常居所は中国であるから,中国法が準拠法となる。
3 中国法における規定等
(1)中華人民共和国婚姻法(1981年1月1日施行,以下「中国婚姻法」という。)には,以下の規定がある。
36条 父母と子女との間の関係は,父母の離婚によって消滅しない。離婚後,子女が父又は母のいずれに直接扶養されるかにかかわらず,依然として父母双方の子女である。
離婚後も,父母は子女に対し依然として扶養及び教育の権利義務を有する。
(以下略)
37条 離婚後,一方が扶養する子女について,他の一方は必要な生活費及び教育費の全部又は一部を負担するものとし,負担する費用の金額及び期間の長短については,双方で協議し,協議が成立しない場合は,人民法院が判決する。
子女の生活費及び教育費に関する協議又は判決は,子女が必要な時に父母のいずれかに対し協議又は判決が当初定める金額を超える合理的な要求をすることを妨げない。
(2)中国には,司法解釈作業に関する規定が制定されており(法発(2007)12号・最高人民法院2006年12月11日制定),同規定の第5条には,「最高人民法院が公布する司法解釈は,法的効力を有する。」と定められている。そして,養育費については,1993年(平成5年)11月3日付で最高人民法院による「人民法院の離婚事件審理における子女扶養問題の処理に関する若干の具体的意見」という書面(法発(1993)30号・以下「意見書」という。)が公布されている。同意見書によれば,次のとおり記載されている。
7 子女の養育費の金額は,子女の実際の需要,父母双方の負担能力及び現地の実際の生活水準に基づいて決定することができる。固定収入がある場合,養育費は一般的にその月の総収入の20から30%の比率に基づいて支払う。(略)但し,一般的に月の総収入の50%を超えてはならない。
固定収入がない場合,養育費の金額は,当年の総収入または同業の平均収入に基づいて上記の比率を参考に決定する。
8 養育費は定期的に支払わなければならないが,条件がある場合は,一括で支払うことができる。
11 養育費の支払期間は,一般的に子女が18歳までとする
12 未だ独立して生活していない成年に達した子女が,以下の各号のいずれかの事由に該当し,また,父母が支払能力を有する場合,依然として必要な養育費を負担しなければならない。
(1)労働能力を喪失した,または労働能力を完全には喪失していないが,その収入が生活を維持するに不足する場合。
(2)未だ就学中である場合。
(3)独立して生活する能力及び条件を確実に備えていない場合。
4 判断
(1)前記1において認定した事実によれば,判決において,養育費は,各扶養者が自ら負担するものと判断されたから,未成年者については,申立人が負担することとなるが,中国婚姻法37条に基づくと,「子女が必要な時」であれば,申立人は,相手方に対し,必要な生活費及び教育費の負担を求めることは可能であると解される。そして,前記1に認定したところによれば,申立人が現在も職に就いていない状態である一方,相手方が約1041万円の給与収入を得ていることからすれば,本件において,申立人は,相手方に対し,未成年者の養育費の請求をすることができるというべきである。
(2)そうすると,相手方が支払うべき養育費の額が問題となるところ,意見書7項が参考になる。しかし,意見書7項については,「その月の総収入」とは父母双方の収入を指すものであるのか,また,同項の「子女の実際の需要」や「現地の実際の生活水準」は不明であって,意見書7項に基づいて養育費を算定するのは相当ではない。
そうすると,条理に従い,日本における養育費の算定方法を参考にすることが相当である。日本では,未成年者の養育費額を算定するに当たっては,義務者及び権利者の各基礎収入の額(総収入から税法等に基づく標準的な割合による公租公課並びに統計資料に基づいて推計された標準的な割合による職業費及び特別経費を控除して推計した額)を定め,その上で,義務者が未成年者と同居していると仮定すれば,未成年者のために充てられたはずの生活費の額を,生活保護基準及び教育費に関する統計から導き出される標準的な生活費指数によって算出し,これを,権利者と義務者の基礎収入の割合で按分して,義務者が分担すべき養育費額を算定するとの方式(以下「改定標準算定方式」という。司法研究報告書第70輯第2号)に基づくのが相当であるから,本件においても,同様の方式に基づくこととする。
(3)義務者である相手方の収入は,1041万円とするのが相当である。権利者である申立人の収入は,現状,0円であるが,過去において稼働していたことからすれば,稼働能力を有しているものと認めることが相当であり,このことは,意見書7項の規定(固定収入がない場合)にも合致する。
そして,上記のとおり,改定標準算定方式に従い,日本に居住する相手方の収入を義務者の収入とする以上,権利者である申立人の収入についても,日本における収入額を参考するのが相当であるところ,申立人と同年齢(35歳から39歳)で企業規模計・学歴計の女性の平均賃金程度の収入を得る稼働能力があるものと認めるのが相当であり,その収入額は,約397万円(令和2年度)とするのが相当である。
(計算)きまって支給する現金給与額27万3800円,年間賞与その他特別給与額68万8300円
27万3800円×12月+68万8300円=397万3900円
これらの申立人と相手方の収入をもとにし,上記方式に基づく改定標準算定表(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)にあてはめると,相手方が負担すべき養育費の額は,月額10万円とするのが相当である。
(4)相手方は,申立人につき,資産を保有している旨を主張しているところ,仮に,申立人に資産があるとしても,養育費は,生活費であって,生活費は,双方が得る収入から支出されるものであるから,原則として,当事者の有する資産の額等は,養育費の算定に当たって考慮されるものではなく,このような考え方は,意見書7項や前記改定標準算定方式にも表れているところである。そして,本件において,特に,申立人が資産を有することを考慮しなければならない事情は,一件記録上,うかがわれない。相手方の主張は採用できない。
(5)本件審判において形成すべき養育費の始期については,申立人が本件審判手続に先行する調停が申し立てられた令和2年8月とし,終期は,意見書11項に基づき,未成年者が満18歳に達する日の属する月とするのが相当である。申立人は,未成年者が大学を卒業するまでの養育費の支払を求めているが,意見書12項に照らし,現時点で定めることは相当ではない。
5 まとめ
以上によれば,令和2年8月から令和4年3月までの養育費の合計額は,200万円(10万円×20か月)となり,相手方は,申立人に対し,同額を直ちに支払うべきである。また,相手方は,申立人に対し,未成年者の養育費として,令和4年4月から,未成年者が満18歳に達する日の属する月まで,月額10万円を支払うべきである。
よって,主文のとおり,審判する。