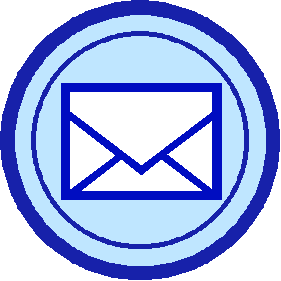離婚後祖父母養子縁組で実親養育料支払義務免除を認めた家裁審判紹介
○事案は事件本人孫と養子縁組をした祖父母が、孫の実父の医者(月収90万円)を相手方として、養子である孫の養育料として月額20万円の支払を求めたものです。相手方医師は、事件本人の実母との離婚に際し、事件本人の20歳までの養育料として120万円を一括支払いしています。
○長崎家裁は、養親は未成熟子の福祉と利益のためにその扶養を含めて養育を全面的に引受けるという意思のもとに養子縁組をしたと認めるのが相当であり、このような当事者の意思及び養子制度の本質からいつて、事件本人に対する扶養義務は先ず第一次的に養親に存し、実親は、養親が資力がない等の理由によつて充分に扶養義務を履行できないときに限って第二次的に扶養義務(生活保持義務)を負うものと解すべきであるとして、申立を却下しました。
*********************************************
主 文
本件申立を却下する。
理 由
一(申立の趣旨)
本件申立の趣旨は『相手方Yと事件本人Aの母Bとの間に福岡家庭裁判所小倉支部において同庁昭和42年(家イ)第5号調停件につき、昭和42年8月28日成立した調停条項第四項を「相手方Yは申立人らに対し事件本人Aの養育料として毎月金20万円宛支払え。」に変更する。』というものである。
二(調停の経過)
申立人両名から昭和50年8月25日相手方に対し事件本人の養育料の支払いを求めて福岡家庭裁判所小倉支部に審判申立があつたので事件は調停に付されたが、合意に至らず調停不成立に終つたところ、同庁の移送の審判により、同51年2月2日当裁判所に本件が係属するに至つた。
三(事実関係)
本件記録添付の各資料及び調査の結果を総合すると次の事実を認めることができる。
(一)相手方と事件本人の実母Bは昭和40年6月14日婚姻し、その間に事件本人をもうけたが、やがて夫婦関係に破綻をきたし同41年7月頃から別居生活を余儀なくしていたところ、同42年8月28日調停離婚し、事件本人の親権者を母Bと定めた。
右調停の際、相手方は前記Bに対し慰藉料(財産分与を含む。)として金100万円を支払う旨取決めたほか、調停条項第四項として「相手方は右Bに対し事件本人が満20歳に達するまでの養育料として金120万円を昭和43年12月末日限り支払う。」旨定めるとともに、同第五項に「今後相互に名義の如何を問わず金銭その他一切の請求をしない。」旨定め、相手方は、約定どおり慰藉料はもとより養育料も全額支払つて債務を履行した。
(二)右離婚後、事件本人は、その親権者である母Bを代諾権者として昭和42年9月26日申立人両名の養父であるCの養子となる縁組を結び、さらに、翌27日右Cを代諾権者として申立人両名と養子縁組をした。右C及び申立人両名はいずれも事件本人の直系尊属にあたる。
なお、右各縁組は相手方には何らの交渉もなく取り結ばれた。
(三)申立人両名は事件本人B及び事件本人の実母Bと共に肩書住所地に在る木造瓦葺2階建居宅(建坪約230平方米)で生活を営んでいる。
申立人両名は、昭和50年1年間に合せて金302万3570円(県・市民税年額28万4920円及び固定資産税、都市計画税等79万4124円を控除した残額)の収入があつたので、これを月割にすると月額金25万1964円の収入となるところ、右収入の外に北九州市戸畑区に両名合せていわゆる課税標準価格で約1億2260万円相当(一般の取引価額よりもかなり低く評価されていることは周知の事実である。)の不動産を所有している。
なお、事件本人の実母Bも昭和50年の1年間の収入が約金122万4231円(県・市民税、固定資産税、都市計画税等を控除した残額)あつたので、月割にすると約金10万2000円の収入となるところ、右収入の外に北九州市戸畑区に土地33筆(共有名義のも含む。)及び家屋を所有している。(右不動産に対する課税年額が合計約110万円にも達していることに徴すると、その課税標準価格は少なくとも1億円を超えると推認される。)
(四)相手方は、医師であるが、昭和45年3月24日Dと再婚し、その間に長男E(同46年3月10日生)をもうけ、同妻子を扶養しているほか、養父母をも扶養しており、現に肩書住所地の借家で外科医院を開設し、税金その他諸種の必要経費等を控除した扶養料算定の基礎収入として月額約90万円程度の所得がある。
四(判断)
本件申立は、前記昭和42年に成立した調停において設定された養育料の一括払債務に関する調停条項の変更を求めているものであるが、相手方が同条項に定められた養育料債務を本件申立以前に既に全部履行し、変更の対象・基礎となるべき養育料債権がもはや消滅している以上、その変更を求めることは許されないものと解されるところ、養育料の性質上、たとい将来の養育料を一括払いし、扶養義務を終局的に打切りとする合意が成立していたとしても、これによつて扶養義務者は常に全面的にその義務を免れうるものではなく、事情如何によつては再びその義務を負担することがあり得ることに鑑み、本件申立の趣旨を昭和50年8月25日(審判申立日)以降の事件本人の養育費の分担を求めているものと善解し、以下前認定の事実関係を基にして判断を進めることとする。
要旨
(一)申立人両名は自己の直系卑属(孫)であり、未成熟子である事件本人を養子とし、一体的共同生活を営んでいるものであるから、このような場合、事件本人の実母も申立人らと生活を共にしながら、事実上事件本人に対する監護権を代行しているとしても、通常一般の縁組と同様、未成熟子である事件本人の福祉と利益のために,親の愛情をもつてその養育を、扶養をも含めて全面的に引受けるという意思のもとに養子縁組をしたと認めるのが相当であつて、このような当事者の意思からいつても、養子制度の本質からいつても、事件本人に対する扶養義務は先ず第一次的に養親である申立人両名に存し、養親が親としての本来の役割を果しているかぎり、実親の扶養義務は後退し、養親が資力がない等の理由によつて充分に扶養義務を履行できないときに限つて、実親である相手方は次順位で扶養義務(生活保持の義務)を負うものと解すべきである。
また、家庭裁判所の許可を要せずして養子縁組をすることができるような場合に、もし養親たるべき者の養子縁組の意思が、未成熟子の親権者となつていない実親からの扶養料を目当てにし、或いは実親の資力如何によつて左右されることがあるとすれば、それは養子縁組の本質に反するものであるのみならず、親権者でない実親にとつても、資力が充分あつて家庭的、人格的諸事情にも欠けるところがなく、しかも子を引取る意思を有しているのにかかわらず、養子縁組につきその意思を何ら問われることもないままに縁組が結ばれて、養親と同順位で生活保持の義務を負うに至ることは不合理であつて、この点からも、実親の扶養義務は第二次的なものとするのが妥当といわなければならない。
(二)そこで、申立人両名の事件本人を扶養する資力の有無、程度について検討するに、申立人両名は、合わせて月額約25万円の収入を得ているところ、次の諸事情、すなわち、北九州市における昭和50年度の一世帯(単身者世帯並びに農家、漁家、料理飲食店、旅館、下宿を含まない。)あたり一か月間の消費支出総額(1年間の平均値)は世帯人員3・86名(世帯主年齢42、3歳)で約16万4878円(3名に換算した額は12万8144円となる。)であること、厚生省告示第85号により改正され昭和50年4月1日から適用の生活保護基準を参酌して、北九州市(一級地)に居住する申立人両名及び事件本人3名の最低生活費を算定すると月額約6万5000円(別紙計算表(一)(略)のとおり)となること、事件本人が申立人両名との共同生活において受けるべき生活費は約8万円であつて、小学5年生の必要生活費としては通常一般の水準をはるかに超過しているといえること『(消費単位には生活保護法による生活保護基準の比率(別紙計算表(一)(略)中基準生活費第一類)を用いるのが相当であるので、これにより按分算定すると、約8万円(別紙計算表(二)(略)のとおり)となるところ、これを厚生省の昭和42年度児童手当制度基礎調査結果にみられる家計総支出額に占める児童養育費の割合を参酌して換算した結果は約2・4人分の養育費に相当する。)』などに照すと、申立人両名の収入は事件本人をも含めて家族3人の生活を維持するに充分というべく、むしろ通常一般よりもはるかに高水準の生活を営むに充分な収入を得ていると認められる。
そればかりでなく、申立人両名は、いわゆる資産家としてばく大な不動産を所有しており、これらの一部を換価して自己需要を補足することも期待できること、その他一切の事情をあわせ考えると、事件本人を養育するに充分な資力を有する申立人両名が、次順位で扶養義務を負うところの相手方に対して養育費の分担を請求するのは失当というべきである。
(なお、事件本人の実母Bも申立人らと同一世帯を構成しているが、同Bは月額約10万円の収入を得ており、申立人らとの共同生活においてむしろ申立人らを扶助する経済的余力があることが窺えるので、同Bを除外して生活程度を検討しても申立人らにとつて不利益な結果をもたらすものではない。)
(三)以上の次第であるから、更に進んで検討を加えるまでもなく、申立人両名の相手方に対する本件申立は失当として、これを却下することとし、主文のとおり審判する。
(家事審判官 山田勇)