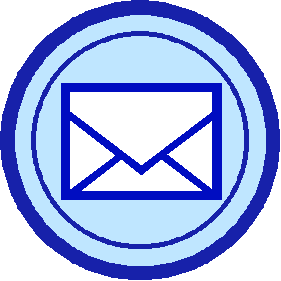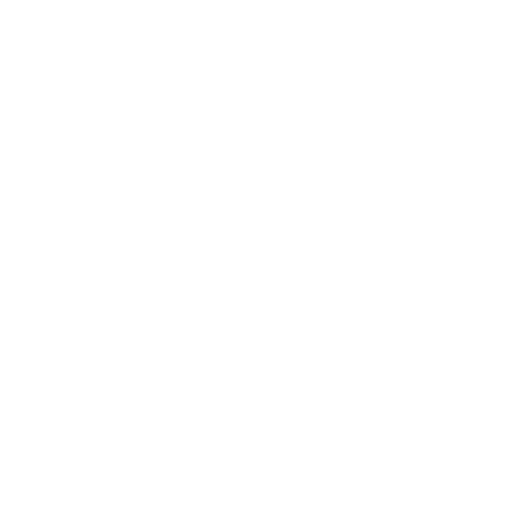期間2年4ヶ月の不貞行為に慰謝料150万円の支払を認めた地裁判決紹介
○この事件では、不貞行為に及んだ妻Cにも原告夫に対する責任があるはずですが、この点について全く触れられておらず、且つ、Cは証人として出廷して、原告夫に有利な証言をしています。この状況で不貞行為第三者の被告に原告夫が損害賠償請求をするのは、美人局を認めるに等しいような気がしますが、150万円も慰謝料を認めています。当事者表示では被告には弁護士が代理人としてついておらず、本人訴訟のようです。被告にも弁護士が代理人としてつけば、被告に有利な主張をできたと思われます。
○判決内には「Cから,被告に対する慰謝料請求を受任した弁護士」との記述があり、妻Cは不貞行為相手方の被告と間に何らかの紛争が生じていたようです。
********************************************
主 文
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する令和元年11月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する令和元年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 原告は,被告が,原告の当時の配偶者と不貞行為に及んだと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料500万円及びこれに対する不貞行為が終了した日である令和元年9月25日から支払済みまで民法所定(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
2 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。なお,以下においては,証拠について枝番を全て挙げる場合には,枝番の記載を省略する。)
(1)原告は,平成4年9月,C(以下「C」という。)と婚姻し,Cとの間に長女(平成7年○○月生)をもうけた。(甲1)
(2)被告は,平成29年5月11日から令和元年11月27日までの間,複数回,Cと不貞行為に及んだ(以下「本件不貞行為」という。)。(甲15,証人C,被告本人)
(3)原告は,令和2年1月,本件不貞行為を知り,同年6月,Cと離婚した。(甲1,6)
3 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,〔1〕被告の故意又は過失の有無,〔2〕損害額である。
(1)争点1(被告の故意又は過失の有無)
(原告の主張)
被告は,Cが既婚者であることを認識していたから,被告には故意がある。
(被告の主張)
被告は,Cが既婚者であることを知らなかった。
(2)争点2(損害額)
(原告の主張)
被告がCと2年4か月余りの間不貞行為を働いたことにより,28年間円満であった原告とCとの婚姻関係が破たんし,原告とCとは協議離婚するに至った。この精神的損害に対する慰謝料は500万円が相当である。
(被告の主張)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(被告の故意又は過失の有無)
(1)証人Cは,被告に対してCに配偶者がいることを伝えており,被告も,Cの配偶者に関する話をしていたなどと供述する。
そこで,その供述の信用性について検討すると,被告は,平成28年7月,C及びその長女と屋形船で食事をしたこと(甲4の1,16の1,16の2)からすれば,被告は,その長女の父,すなわちCの配偶者が存在することを認識する契機があったといえる。
また,被告は,本件不貞行為の期間中である令和元年8月13日,Cに対し,Cの周りには「ご主人様とお母様とDちゃんとEちゃんと荻窪警察と弁護士」がいる旨のメールを送信しており(甲10の3、証人C),Cの配偶者の存在を前提とする内容のメールを送信していた。
さらに,Cから,被告に対する慰謝料請求を受任した弁護士は,令和2年3月3日,被告と面談し,その後,Cに対し,被告の発言要旨を報告したところ,その発言要旨の中には,被告は,被告にもCにも家庭があるので安心していた感があったとの記載がある(甲8,9)。
以上によれば,被告は,Cに配偶者がいることを認識していたと強く推認され,このことは,証人Cの上記供述を裏付けている。
(2)これに対し,被告は,Cが既婚者であるとは知らなかったと主張し,被告本人も,Cの婚姻関係については知らなかったとか,Cから,Cには同居人がいるものの顔を合わせることはないと聞いていたなどと供述する。
しかしながら,Cとその同居人との関係に関する被告本人の供述はあいまいで具体性を欠くし,また,被告がCの自宅内に入ることはなかったこと(被告本人)からしても,被告がCに配偶者がいると認識していなかったとは考え難い。
したがって,被告本人の供述は,前記(1)の推認を覆すものとはいえず,採用することはできない。
(3)そうすると,証人Cの供述によれば,被告は,Cに配偶者がいることを認識していたと認められ,被告は,本件不貞行為につき故意による不法行為責任を負う。
2 争点2(損害額)について
本件不貞行為の発覚を契機に原告とCとは離婚に至ったというべきであること(甲6),その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料を150万円とするのが相当である。
3 小括
以上によれば,原告は,被告に対し,不法行為に基づき,150万円及びこれに対する本件不貞行為が終了した日である令和元年11月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる(なお,原告は,被告がCと少なくとも125回不貞行為に及んだと主張していることなどに照らせば,被告の不貞行為全体に対する慰謝料を請求していると解され,その遅延損害金は,本件不貞行為が終了した令和元年11月27日から発生する。)。
第4 結論
よって,原告の請求は,上記の限度で理由があるから,その限度でこれを認容し,その余は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第37部裁判官 岩田真吾