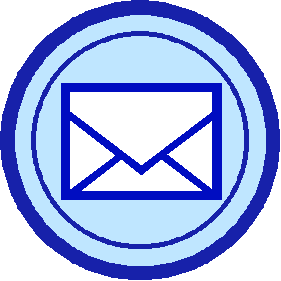財産分与600万円不貞行為慰謝料200万円を認めた地裁判決紹介
○原告(反訴被告)の妻が被告(反訴原告)の夫に対し、原被告の婚姻関係の破綻は被告の不貞及びその他の有責行為によるとして民法770条1項1号及び5号により、、2人の女児(13歳、7歳)の親権者を原告に指定しての離婚と、財産分与として600万円、被告の不貞等の慰謝料1000万円の支払を求めました。
○これに対し、判決は、原被告間の離婚を認め、2人の子の親権者を原告とし、被告が原告に対し財産分与として600万円を、慰謝料として200万円を支払うよう命じました。どういう訳か公開されている判決文は、当事者の主張のみで理由は省略されています。字数の関係で、被告(夫)の反訴主張も省略します。
○この判決の控訴審である昭和53年2月27日東京高裁判決(最高裁判所民事判例集32巻8号1542頁)では、一審原告(妻)は財産分与請求額を600万円から2000万円に請求拡張し、財産分与1000万円、慰謝料300万円が認められています。
○昭和53年2月27日東京高裁判決(最高裁判所民事判例集32巻8号1542頁)の上告審が昭和53年11月14日最高裁判決(判タ375号77頁)で、夫婦の一方が負担すべき婚姻費用の支払を怠り,他方が過当にこれを負担している場合、最高裁判決は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるとしました。
****************************************
主 文
一 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。
二 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長女A(昭和38年5月23日生)、二女B(昭和44年2月11日生)の親権者をいずれも原告(反訴被告)と定める。
三 被告(反訴原告)は原告(反訴被告)に対し金800万円を支払え。
四 原告(反訴被告)のその余の請求を棄却する。
五 被告(反訴原告)の請求を棄却する。
六 訴訟費用は本訴反訴を通じこれを3分し、その1を原告(反訴被告)、その余を被告(反訴原告)の負担とする。
七 この判決は、第三項のうち金200万円にかぎり、仮に執行することができる。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
(本訴について)
一 原告(反訴被告、以下単に原告という)
(一) 主文1、2項同旨
(二) 被告(反訴原告、以下単に被告という)は、原告に対し、金1600万円を支払え。
(三) 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第二項のうち金1000万円の部分につき仮執行の宣言を求める。
二 被告
(一) 原告の請求をいずれも棄却する。
(二) 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
(反訴について)
一 被告
(一) 主文一項同旨
(二) 原告と被告との間の長女A、二女Bの親権者をいずれも被告と定める。
(三) 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
二 原告
(一) 被告の請求を棄却する。
(二) 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第二 当事者の主張
(本訴について)
一 原告
(一) 原告は、昭和30年6月から昭和37年2月まで岩手県教育委員会(以下県教委という)教育長をしていた訴外C正雄(以下Cという)の長女であり、昭和35年3月静岡県立女子短期大学を卒業し、同年4月から盛岡市の白百合学園中学校の教師をしていたものであり、被告は、学校法人修紅学院(以下学院という)の理事であつた訴外小梨D(以下、Dという)の二男であり、昭和27年4月学習院大学政経学部に入学し、昭和32年3月同大学を中途退学して教員の資格がないにもかかわらず、これあるかのごとく装つて右学院の高等学校で英語、倫理、社会等を教えていたものであるが、昭和36年7月ころDと相謀り、学歴を学習院大学卒業であり、将来学院高等学校の校長に任命される予定であるとか、新婚旅行はアメリカにしたい、新居を建ててやるなどと偽り、当時県教委委員長をしていた訴外E佐十郎(以下、Eという)を仲に立てて原告に求婚してきたので、原告は、右言を信じ、昭和36年12月28日結婚式を挙げ、翌37年2月19日婚姻届をなして夫婦となり、昭和38年5月23日長女A(以下Aという)が、昭和44年2月11日二女B(以下Bという)が生まれた。
(二) 原被告は、昭和37年4月から一関市城内(当時釣山といつた)の借家に暮らすようになつたが、間もなくDが原告に対し、被告には「他にいい候補がいたのに、晴子(原告)に決めて惜しいことをした」とか原告側で「仲人料をケチつたばかりに苦労する」などと侮辱し始め、被告もこれに加担して原告を嘲笑揶揄するしまつであり、被告はやがて飲酒麻雀等に耽るようになり、深更に帰宅することが多く、早く帰宅したときには必ず多数の同僚の教員らを引き連れ、深夜まで遊び興じ、原告に酒食などのサービスを強いた。右被告の生活態度は昭和38年5月23日Aの生まれたころから一段と不規則となり、原告は、そのために休息がとれず健康を損うようになり、被告に節制を求めたが、怒鳴り返されるしまつで、Dに相談したところ「学校のためによかれとやつているのだから嫁は男の仕事に一切口出しするものではない」と説教されたため、以後黙つて耐え忍んでいたところ、被告の態度はますます放縦になつた。
(三) 原被告の家計は、長女誕生までは月1万円、その後は毎年約5000円の増額がなされたが、その生活は楽ではなく、原告が婚姻前に貯えていた約50万円の貯金をこれに振り向けてきた。更に、被告は、原告に学院の人件費節約のためとして、婚姻後右高校において英語の授業を担当させたが、その受くべき給与の内容を一切原告に秘し、その支給額をすべて被告が受領していた。
(四)
1 原告は、昭和41年ころから被告の不貞に気づき懊悩したが、被告は、次に述べる以外にも教え子に妊娠させるなど不倫を重ねた。
2 被告は、昭和41年1月の冬休み中、同僚教師のF誠子(以下、Fという)、生徒のHG(以下Gという)、同H啓子の3名と生徒会費を使い、原告に対しては体育関係の講習会に出席すると偽つて、青森県浅虫温泉に旅行に出かけ、その夜、一人では淋しいからと同伴者らにジヤンケンをさせ、勝つたFと自室に宿泊して情を通じ、その後も情交関係を続けた。
3 被告は、同月進学指導に言寄せてGを放課後教室に残し、暴力をもつて姦淫しようとしたが、同女の抵抗にあいその目的を達することができなかつた。
(五) 被告及びDが中心となつて、昭和43年3月ころ、学院高校の教員数名を解雇したことから端を発し、激しい学園紛争に発展し、原告のもとに連日抗議の文書や電話が掛かるようになり、さらに、当時学院の理事長であつた訴外小梨I(以下Iという)からも、被告を罷免する旨の電話が掛かるようになつたが、被告は何の対策も講じないばかりか、飲酒しては深夜帰宅することをくりかえしたために、原告は疲労困憊の極に達し、同年6月16日、被告とDの了解を得て、神奈川県藤沢市所在の実家に帰り静養することになつた。
(六) Cは、静養に帰つてきた原告が持参した、「被告は学習院大学を除籍され教員の免許はない」との抗議文を読み、同月末同大学を訪ねて右事実を照会したところ右事実のとおりであるとの回答を得、被告に電話して、Dと二人で謝罪し今後の方針を示さない限り原告は返さない旨伝え、同年8月初め、東京都新橋の第一ホテルで被告及びDと会つたが、両名は、被告が学院を退職した上、上京してどこかの大学に復学すること、右につき月10万円の生活費を送るとの同年7月27日の理事会で決まつた事項をくりかえすだけで、謝罪の言葉はなく、怒つたCのもとに、被告は、Cから示唆されて初めて、同年8月8日、誓約書と題する書面を持参して来、同月16日、Iが謝意を表わした書面を持参して来て、その際、Iは被告が10年以上も無免許で自動車を運転し、事故を起こしたことがあること、その他素行の上でいろいろ問題があるが注意しても効果が無い旨を述べた。原告は、被告の学歴詐欺やにせ教師であるということはあくまでも信じられなかつたが、同年8月中ころ、学習院大学を訪れ、右事実を確認し、被告に失望して離婚を考えるようになつた。
(七) Cは、原被告の婚姻生活を案じ、Cの提唱によつて、同年9月8日、一関市において、被告及びDの謝罪と被告の今後の方針を明確にすべく、原被告双方の親族による会合が開かれたが、Dは気分が悪いと出席せず、被告の態度も不遜であつたが、大学に復学し、教職員免許を得たうえで帰郷して学校経営に当るということであつたので、Cは、右会合に出席していなかつた原告に、東京での被告の更生を期待して一緒に生活するよう説得した。
(八) 原告は、Cに説得され、被告とともに東京での生活に備えて東京都世田谷区若林町の「松陰メゾネツト」というマンシヨン(以下マンシヨンという)に住居を定め、同年9月末、一関市に帰つたが、Dからは何ら謝罪の言葉すらなく、同年10月初めから原被告は、東京で生活を始めた。被告は国士館大学事務局に事務員として勤務する傍ら、夜は同大学政経学部二部経済学科に通学することになつた。
原被告間には、昭和44年2月11日Bが生まれ、原告は被告の勉学を励ましたが、被告は夜遊びに興じて何ら更生の兆なく、同年3月末、そのころ施行の某大学の入学試験問題を、かつての教え子に漏らし、右をたしなめた原告に対し、「要らざることに口出しをするな」と怒鳴りかえすしまつで、その後も、被告の夜遊びは続き更生の態度が見受けられないため、ついに同年7月19日離婚を決意して原告肩書住所地のCのもとに子供二人を連れて帰つてきた。
(九) 原告は、右別居に当たり、額面300万円の割引興業債券を持ち帰つたが、右は、もともと、原被告の生活資金であり、別居後、被告からの送金を望めないために原告と子供らの生活費の一部に当てる目的で持ち帰つたものであり、別居以来今日まで被告からの生活費の仕送りはなく、その間原告が費した子供らを含めての生活費等は約1千万円にのぼる。
被告は、原告と婚姻後、Dの援助もあつて月数十万円の預金ないし債券の購入をし、今日、右資産だけでも3000万円を超えるだけでなく、昭和43年、一関市田村町に1483・27平方メートルの土地をDとそれぞれ2分の1の持分をもつて取得し、右評価額は、被告の持分だけでも4300万円を超える。
(10) 以上のように、原被告の婚姻関係の破綻は、被告の不貞及びその他の有責行為によるものであつて、原告は、民法第770条第1項第一号及び第五号により、被告との離婚を求めるとともに、右離婚に伴い、財産分与として金600万円及びA、Bの親権者を原告と定めることを求め、被告の不貞及びその他の有責行為により被つた原告の精神的苦痛を慰藉するには金1000万円が相当であるから、右不法行為に対する慰藉料として右金員の支払を求める。
二 原告の主張に対する被告の答弁
(一) 原告の主張(一)のうち、原被告の経歴、新婚旅行、新居の建設の話、婚姻、子の出生は認め、その余は否認する。Cは、昭和36年当時、県教委教育長及び私学事務局長などの職にあつて、被告が教員の免許を有しないことを知りながら、原告に被告との婚姻を積極的にすすめたものである。アメリカに新婚旅行に行く話は原告の意見もあつてとりやめたものであり、新居建築については、原告の意見や、候補地の関係もあつて手頃の土地が見つかつてからということになり、原被告は新築資金に充てるため、預金していたほどである。
(二) 同(二)のうち、被告の嫁の候補が他にいたことを認め、その余は否認する。
(三) 同(三)のうち、原告が学院高校の教鞭をとつたことは認め、その余は否認する。原被告の生活については、Dが家賃から食料品、原告の小遣に至るまで負担しており、原告に不自由させたことはない。
(四) 同(四)の1、2、3はいずれも否認する。
(五) 同(五)のうち、学院の教員解雇から学園紛争が生じたこと、原告がその主張のころ実家に帰つたことは認め、その余は否認する。右教職員の解雇は、Cの指導のもとに行なつたものである。
(六) 同(六)のうち、原告主張のころ、被告及びDがCと会つて話したこと、被告及びIが誓約書を持参したこと、被告が無免許運転をして交通事故を起こしたことは認める。
昭和43年7月26日の学院の理事会において、被告の退職を認め、被告が上京のうえ大学を卒業して、高等学校教員免許を得、時期を見て学院に復職させること、右勉学のため必要な資金は被告の学院に尽くした労に報いるため退職金として金250万円を支給することが決まつたので、Dは、原告及びCと原被告のことにつき話し合うため、連絡をとつて、同年8月上旬東京新橋の第一ホテルでC夫婦とあつたが、Cは時候の挨拶をするまもなく被告らを怒り、テーブルをたたいて罵詈雑言を浴びせ、被告らは恐ろしさのあまり一言もいえなかつたものである。
(七) 同(七)のうち、原告主張のころ一関市で会合が開かれたことは認める。
(八) 同(八)のうち、昭和43年10月初めからマンシヨンで一緒に生活するようになつたこと、被告が国士館大学事務局に事務員として勤めるとともに、同大学政経学部二部経済学科に編入学するようになつたこと、原告主張の日にBが生まれたこと、昭和44年7月19日、原告が子供2人を連れて実家に帰つたことは認め、その余は否認する。
(九) 同(九)のうち、Dと被告が一関市田村町にそれぞれ2分の1の持分をもつて土地を所有していることは認める。原告が持ち帰つたのは額面400万円の割引興業債券並びに原告及びA名義の金150万円の定期預金である。右は前記退職金250万円、及び上京前被告名義の一関市城内の約70坪の土地の売却代金約400万円等であつて、マンシヨン代はDが全額負担し、生活費としては、右退職金が約2年分として月10万円が予定されており、何不自由のない生活であつた。
なお、被告は、婚姻後原告に対しダイヤ・エメラルド・オパール・アメジスト・トルコ石など購入時の価額で数百万円に達する十数個の宝石入り指輪を買い与えており、原告は別居に際し右をすべて持ち帰つており、現在の価格にすれば1000万円を超えるものである。
(中略)
第三 証拠関係(省略)
(中略)
(昭和51年9月24日 東京地方裁判所民事第一部)