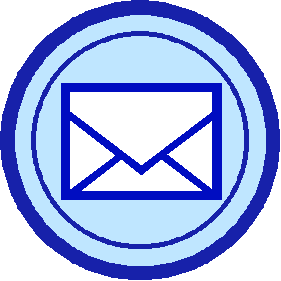オーバーローン不動産住宅ローン返済分の共有持分を認めた地裁判決紹介
○原告元夫が、本件建物は自己の単独所有であるにもかかわらず、これを専有している元妻を被告として、所有権に基づき、元夫名義建物の明渡と、所有権侵害の不法行為に基づき、月額約20万円の使用料相当損害金の支払を求めました。
○これに対し、原告被告間の離婚訴訟の本件控訴審判決を担当した裁判所は、元夫名義不動産を財産分与の計算対象から外していることから、離婚訴訟の財産分与とは別個に、元夫名義不動産の権利関係を確定し、その精算に関する処理がなされるべきであるところ、本件不動産の購入・建築にあたり、被告元妻の固有財産からも相当額の支出がなされていることから、本件不動産のうち少なくとも持分3分の1については、被告元妻の持分に属するものであると認定し、原告の使用料相当損害金請求の一部のみ認容した平成24年12月27日東京地裁判決(判時 2179号78頁)を紹介します。
○平成25年6月にも紹介していましたが、重要判決なので再度の紹介です。
********************************************
主 文
一 被告は、原告に対し、平成24年5月7日から別紙物件目録記載二の建物明渡済みまで1か月10万円の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、これを5分し、その4を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
一 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載二の建物を明け渡せ。
二 被告は、原告に対し、平成24年5月7日から前項の建物明渡済みまで1か月19万8000円の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要等
本件は、原告が、別紙物件目録記載二の建物(以下「本件建物」という。)は自己の単独所有であるにもかかわらず、これを被告が占有しているとして、被告に対し、所有権に基づき、本件建物の明渡しを求めるとともに、所有権侵害の不法行為に基づき、被告の本件建物占有開始時から明渡済みまで月額19万8000円の割合による使用料相当損害金の支払を求めた事案である。
一 前提事実(証拠等により明らかに認められる事実)
(1) 原告(昭和46年○月○日生)と被告(昭和45年○月○日生)は、平成13年2月18日に婚姻した元夫婦であり、平成17年○月○日に長女Aを、平成20年○月○日に長男Bをそれぞれもうけた。
(2) 原告と被告は、平成14年11月9日、別紙物件目録記載一の土地(以下「本件土地」という。)を購入し、同日、原告名義の登記を了した。原告と被告は、平成15年5月14日、本件土地上に本件建物を新築し、同月30日、原告名義の登記を了した。原告と被告は、平成15年5月に本件建物に入居した。
(3) 被告は、美容師の資格を持ち、原告と婚姻後、実家の美容院を定期的に手伝っており、長女が生まれた後も、実家の手伝いをしていた。長女の日常の世話は主に被告が行っており、長男の出産を控えた平成20年1月末までは、主として自宅で長女を監護し、被告が実家に手伝いに行くときは長女を連れて行った。
(4) 原告は、平成20年5月26日、被告に無断で長女及び長男を連れて本件建物を出て、被告が本件建物に残った。原告は、その後、知人宅や実兄宅等を経て、兵庫県加古川市内のアパートで生活するようになった。
(5) 被告は、平成20年8月14日、原告を相手方として、神戸家庭裁判所姫路支部に対し、子の監護に関する処分(子の監護者の指定、子の引渡し)を求める手続を申し立て、原告は、同年10月30日の調停期日において、長女及び長男を被告に引き渡した。
(6) 原告と被告が婚姻後形成した共有財産は、本件土地及び本件建物(以下併せて「本件不動産」という。)並びに原告名義の預金である。なお、原告の平成20年6月から平成21年5月までの年収は約1000万円であった。被告は、その当時、家事手伝いをして無収入であり、子らは、日中は、長女は保育園に、長男は家庭福祉員に預けていた。
(7) 被告は、平成20年8月14日、原告を相手方として、東京家庭裁判所に対し、夫婦関係調整調停及び婚姻費用分担調停を申し立てた。同年10月14日に調停期日が開かれたが、原告は、同期日後、被告が帰宅する前に、本件建物まで赴き、鍵を開けて本件建物に入ろうとしたが、被告が予め鍵を交換していたため本件建物に入ることができなかった。原告は、いったん鍵屋を呼び、破壊しなければ開かない鍵であることを告げられるや、鍵を破壊して本件建物に入ろうとしたが、鍵の破壊に手間取ったことからこれを中止した。
(8) 原告は、平成20年7月ころまでは本件建物において生活していたが、その後遅くとも上記子らの引渡しを受けた日以降は、本件建物から自転車で20分ほどの場所にある実家で生活するようになった。ただし、原告は、実家で生活するようになってからも、本件建物内に少なくとも子らのベビーダンス及び収納ボックス等を置いていた。
(9) 平成20年11月27日、前記婚姻費用分担調停申立事件につき調停が成立し、原告が、被告に対し、同年12月から当事者の別居解消又は離婚に至るまで婚姻費用分担金として月額10万円を支払うことのほか、被告が居住している本件建物にかかる住宅ローンについて、原告がこれを負担すること等が合意された。
(10) 平成21年、被告は、原告を相手として、東京家庭裁判所に対し、原告との離婚、子らの親権者となること、養育費、財産分与及び慰謝料を求めて訴訟を提起し、これに対し、原告も、被告を相手として、東京家庭裁判所に対し、被告との離婚、子らの親権者となること、財産分与及び慰謝料を求めて訴訟を提起し、両事件は併合されて審理が行われた。東京家庭裁判所は、平成22年2月26日、原告と被告とを離婚し、子らの親権者をいずれも被告とすること、養育費として原告が被告に対し子1人につき月額7万円を支払うこと、財産分与として原告が被告に対し1058万5458円を支払うこと、慰謝料として原告が被告に対し250万円余りを支払うことを内容とする判決(以下「本件第一審判決」という。)を言い渡した。
(11) 原告は、本件第一審判決を不服として、東京高等裁判所に控訴を提起した。東京高等裁判所は、平成22年8月25日、本件第一審判決のうち、養育費について原告が被告に対し子1人につき月額4万円を支払うよう、財産分与について原告が被告に対し707万0598円を支払うよう判決内容を変更するとともに、その余の控訴を棄却する旨の判決(以下「本件控訴審判決」という。)を言い渡し、同判決は、同年9月9日に確定した。
(12) 本件控訴審判決言渡後、被告は、被告代理人を通じて、原告に対し、本件建物に居住する予定であることを伝えていたことから、原告から原告代理人を通じて本件建物の鍵の引渡しを求められても、これに応じない旨回答した。
(13) 原告は、平成22年9月11日ころ、鍵屋を呼び、本件建物の鍵を損壊して解錠し、新たな鍵を取り付け、その後本件建物に居住している。被告は、同年10月6日、本件建物に赴いたが、鍵を開けることができなかったため、インターホンを鳴らしたところ、原告がこれに応答し、原告と被告は言い争いになった。
(14) 被告は、平成23年2月8日、原告を相手として、東京地方裁判所に対し、占有権に基づき本件建物の返還(明渡し)を求めるとともに、占有侵奪の不法行為に基づき損害賠償(慰謝料)を求める訴訟を提起した。東京地方裁判所は、同年12月22日、原告が被告に対し本件建物を明け渡すとともに慰謝料20万円余りを支払うよう命じる内容の判決を言い渡した。原告は、上記判決に従い、平成24年5月7日、被告に本件建物を明け渡した。
二 争点
(1) 本件建物は原告が単独所有しているか(争点(1))。
(2) 本件建物の一か月あたりの使用料相当損害金はいくらか(争点(2))。
三 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件建物は原告が単独所有しているか)について
ア 原告の主張
既に確定している原告被告間の離婚訴訟の本件控訴審判決では、原告と被告の共有財産について、「第三 二(2) 原判決の付加訂正」のイにおいて、本件第一審判決の7頁20行目の「別表記載のとおりである」を訂正し、本件不動産及び原告名義の預金と改めている(7頁4行目から9行目)。そして、「第三 五(1)」において、本件不動産の評価額並びに住宅ローンの残債務額を考慮して「残余価値は0円と評価するのが相当である」として(9頁11行目から12行目」、「第三 五(3)」において、本件不動産の価値を考慮した上で、財産分与額を707万0598円と判示している。上記のとおり、本件控訴審判決では、本件建物が財産分与の対象財産とされていることは明白であり、その価値が残債務額を併せて考慮された結果、0円と評価されたにすぎない。
このように、本件建物については、原告被告間の本件控訴審判決において夫婦共有財産とされた上で財産分与額が算定されているのであって、本件控訴審判決の確定により、現在はその名義人である原告の単独所有に属するものである。
イ 被告の主張
本件控訴審判決は、「第三 五 財産分与について」の項目中、「(1) 不動産(本件不動産)」の箇所において、「上記土地建物(本件不動産)の価格は、これらに設定された抵当権の被担保債権(住宅ローン)の残債務3178万3851円とほぼ同程度であり、残余価値は0円と評価するのが相当である」と判断し(9頁9行目から12行目)、当事者の主張どおり、本件不動産を財産分与の対象財産から外す旨の認定をした。その上で、本件控訴審判決は、財産分与に関し、原告と被告の別居時に残存していた原告名義の預金の合計額を2分の1にし、その金額から原告から被告へ別居開始後に支払済みの金員の額を控除し、原告が被告に対し707万0598円を支払うよう判示した(10頁1行目以下)。
このように、原告被告間の離婚訴訟における財産分与の対象は原告名義の預金のみとされ、本件不動産はこの財産分与の対象から外されたものである。そして、本件不動産に関しては、①被告の解約した預金800万円、②原告と被告が同居していた間に支払われた住宅ローンの返済総額の2分の1相当額(290万8601円)、及び③原告と被告の別居時から離婚時までの間の住宅ローンの返済額のうち計220万円(平成20年12月から平成22年9月分までの住宅ローンの支払分のうち月額10万円に相当する額)の合計1310万8601円については、被告の固有財産から支払われたものと評価することができるから、本件不動産は現在でも原告と被告の共有財産として取り扱われるべきである。
(2) 争点(2)(本件建物の一か月あたりの使用料相当損害金の額)について
ア 原告の主張
本件建物の一か月あたりの使用料相当損害金は19万8000円が相当である。
イ 被告の主張
本件建物の1か月あたりの使用料相当損害金はせいぜい7万円程度である。
第三 当裁判所の判断
一 争点(1)(本件建物は原告が単独所有しているか)について
(1) そもそも、夫婦間の財産分与は、夫婦共同生活中の共通の財産の清算であり、財産分与の対象とされた財産を金銭的に評価し、そこから負債を控除し、なお積極財産が残る場合に、特段の事情がない限り、その2分の1に相当する額を相互に分与しあうことで、夫婦間の実質的公平を図る制度である。
ところが、住宅ローン残高が不動産価値を上回るいわゆるオーバーローンの不動産や、不動産の価値と住宅ローン残高がほぼ同程度であるとして残余価値がないと評価された不動産は、積極財産として金銭評価されることがないため、夫婦間の離婚訴訟の財産分与の手続においては、清算の対象とはならない。
その結果、夫婦共有財産と判断された不動産について清算が未了のままとなる事態が生じ得るが、この場合、不動産の購入にあたって自己の特有財産から出捐をした当事者は、かかる出捐をした金員につき、離婚訴訟においては、その清算につき判断がなされないまま財産分与額を定められてしまい、他方で、たまたま当該不動産の登記名義を有していた相手方当事者は、出捐者の損失のもとで不動産の財産的価値のすべてを保有し続けることができるという極めて不公平な事態を招来することになる。
そこで、夫婦の一方がその特有財産から不動産売買代金を支出したような場合には、当該不動産が財産分与の計算においてオーバーローン又は残余価値なしと評価され、財産分与の対象財産から外されたとしても、離婚訴訟を担当した裁判所が特有財産から支出された金員につき何ら審理判断をしていない以上、離婚の際の財産分与とは別に、当該不動産の共有関係について審理判断がされるべきである。
(2) これを本件についてみるに、証拠〈省略〉によれば、本件控訴審判決を担当した東京高等裁判所は、本件不動産に関して残余価値は0円と評価するのが相当である旨判断し、財産分与額の計算に際し、本件不動産をその対象から外し、原告名義の預金のみを財産分与の対象としており、そのため、本件不動産については、原告被告間の離婚訴訟における財産分与の規律において処理がされていないことが認められるから、離婚訴訟の財産分与とは別個に権利関係を確定し、その清算に関する処理がされるべきである。
そして、前記第二の一の前提事実に証拠〈省略〉を総合すれば、
①被告は、原告と被告が本件不動産を購入・建築するにあたり、自らが婚姻前に貯蓄した預金を解約して800万円を出捐しており、これは被告の固有財産から支払われたものといえること、
②原告は、被告との婚姻期間中の平成16年3月から、本件不動産の購入時に融資を受けた住宅ローンの支払を開始しており、この住宅ローンの返済は原告の給与が原資となっているところ、原告と被告が婚姻関係にあった時期(別居時を除く。)の原告の給与は夫婦共有財産に属するものであるから、平成16年3月から別居開始時である平成20年5月26日までの間に支払われた住宅ローンの返済総額581万7203円の半分に相当する290万8601円については、被告の固有財産により支払われたものと評価できること、
③原告と被告が別居した後の平成20年12月当時、年間約1000万円の収入があった原告の収入状況からすれば、当時3歳と0歳の子2人を養育していた被告に対して支払われるべき婚姻費用は本来月額約20万円と定められるべきものであったこと、しかるに、当時、原告が本件不動産の住宅ローンを支払っており、その額が年間約130万円程度に上ることや、被告が本件不動産に居住していたこと等を踏まえ、原告の住宅ローン支払分のうち月額約10万円分は原告から被告に支払われるべき婚姻費用の支払分とみなすことができるとして、平成20年12月以降原告から被告に支払われるべき婚姻費用は月額10万円と定められたと推認できること、
かかる経緯によれば、婚姻費用の支払が開始された平成20年12月から、離婚が成立した平成22年9月までの1年10か月の間に返済された住宅ローンのうち合計220万円(1か月あたり10万円の22か月分)については、被告に婚姻費用として支払われる代わりに住宅ローンの支払に充てられたものとみることができるから、被告の固有財産から支払われたものと評価できること、以上のとおりであり、本件不動産に関しては、被告の固有財産1310万8601円がその支払に充てられたものと評価することができる。
したがって、証拠〈省略〉から認められる本件不動産の評価額に照らせば、本件不動産のうち少なくとも持分3分の1については、被告の持分に属するものであることが認められる。
(3) そして、共有物の持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することはできないから(最高裁昭和41年5月19日第一小法廷判決・民集20巻五号947頁)、本件不動産の持分3分の2を有する原告は、本件不動産の持分3分の1を有する被告に対し、所有権(持分権)に基づき、当然には、本件建物の明渡しを求めることはできないというべきである。
二 争点(2)(本件建物の一か月あたりの使用料相当損害金の額)について
(1) 証拠〈省略〉により認められる本件不動産の所在場所、本件建物の建築時からの経過年数をはじめ、本件建物の床面積、土地の地積等を総合すれば、本件建物全体の1か月あたりの使用料相当損害金は15万円と認めるのが相当である。
(2) そして、被告は、平成24年5月7日以降、本件建物のうち被告持分(3分の1)を超える持分3分の2(原告持分)の部分については、権原なくして占有していることが明らかであり、これは原告持分権を侵害する不法行為にあたるから、原告は、被告に対し、不法行為に基づき、平成24年5月7日以降本件建物明渡済みまで月額10万円の割合による使用料相当損害金の支払を求めることができるというべきである。
三 結論
以上によれば、原告の本訴請求は、被告に対し、本件建物の持分権侵害の不法行為に基づく損害賠償として、平成24年5月7日から本件建物明渡済みまで月額10万円の割合による使用料相当損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法61条、64条本文を、仮執行宣言について同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。(裁判官 飯野里朗)