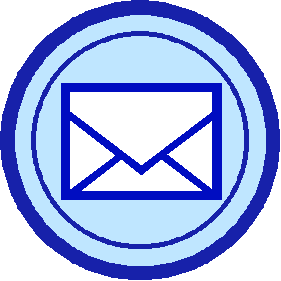婚姻破綻を認め有責配偶非該当として離婚を認めた家裁判決紹介
○夫である原告が、妻である被告に対し、被告の所作に対する忌避感や長期間の別居、原告に無断で原告の父と養子縁組をしたことなど、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、民法770条1項5号に基づき、被告との間の未成年の子である二女Bの親権者を原告と定めて離婚することを求めました。
○判決は、被告に復縁の意思があるとしても、婚姻関係は破綻しており、その修復は極めて困難であるといわざるを得ないから、婚姻を継続し難い重大な事由が認められ、また、原告が有責配偶者であるということはできず、原告の離婚請求が信義則上許されないということはできないとしました。
○また、被告による二女の監護の現状に特段指摘すべき問題があるということはできず、安定した監護の現状を変更すべき事情も見当たらないことなどからすると、子の福祉の観点から、二女の親権者を被告と指定するのが相当であるとして、原告と被告とを離婚するとする一方、原告と被告との間の二女Bの親権者を被告と定めました。
○長期間の別居が続き、誰の目にも婚姻破綻と思われる事案でも、離婚を拒否する側は、関係修復の可能性があると答弁しますが、最も強く主張するのは、離婚請求側の有責性です。有責性というと不貞行為が典型ですが、不貞行為がなくても、離婚を請求する原告に対し、原告は一方的に婚姻破綻を作った有責配偶者であり、身勝手な離婚請求は認めるべきではないと答弁します。
○本件も、「本件訴訟が不当訴訟に当たると再三供述」し、原告の有責性が実質争点になりましたが、結論としては「原告が婚姻継続の意思を失ったことについて、原告を有責配偶者であるということはできない。」とされました。この点は、日本ではまだ有責主義のなごりが強く、有責主義か破綻主義かの裁判官の主観が相当入り、結論は、当たった裁判官によりけりとなります。
********************************************
主 文
1 原告と被告とを離婚する。
2 原告と被告との間の二女B(平成15年×月×日生)の親権者を被告と定める。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 主文第1項と同旨
2 原告と被告との間の二女B(平成15年×月×日生)の親権者を原告と定める。
第2 事案の概要
1 本件は、夫である原告(昭和37年×月×日生)が、妻である被告(昭和41年×月×日生)に対し、被告の所作に対する忌避感や長期間の別居、原告に無断で原告の父と養子縁組をしたことなど、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、民法770条1項5号に基づき、被告との間の未成年の子である二女B(平成15年×月×日生。以下「二女」という。)の親権者を原告と定めて離婚することを求めた事案である。
2 前提事実(各項末尾に掲記した証拠等により容易に認定できる事実)
(1)原告(昭和37年×月×日生)と被告(昭和41年×月×日生)は、平成5年8月×日、婚姻の届出をし、平成9年×月×日、長女C(以下「長女」という。)を、平成15年×月×日、二女(以下、長女と併せて「子ら」という。)をもうけた。
(2)原告は、平成23年6月頃、自宅を出て、以降、現在に至るまで、被告と同居していない。
(3)原告は、平成24年10月10日付けで、被告に対し、離婚訴訟を提起したが(東京家庭裁判所平成24年(家ホ)第937号)、平成25年7月30日、原告の離婚請求は棄却され、原告はこれを不服として控訴したが(東京高等裁判所平成25年(ネ)第5101号)、平成25年10月30日、控訴は棄却され、確定した(以下、この一連の訴訟を「前件訴訟」という。)。
(4)原告は、被告を相手方として夫婦関係調整(離婚)調停(東京家庭裁判所平成29年(家イ)第674号)を申し立てたが、平成29年4月26日、不成立となった。
3 争点
(1)離婚原因の有無
(2)親権者の指定
4 争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(離婚原因の有無)について
(原告の主張)
被告は、専業主婦であり、健康状態に問題を抱えているわけでもないのに、血圧が低い、朝が弱いなどの様々な訴えをして、食事の支度、片付け、掃除等の家事をおろそかにし、生ごみを原告の靴の上に置いたり、原告の服装や外見を誹謗中傷するほか、原告が買い物をすると値段等を執拗に聞いたり、浪費大王などのあだ名を付けるなどした。
また、被告は、東京都北区Dに購入した3LDKのマンション(以下「Dのマンション」という。)における原告の部屋を暗く湿った二畳半ほどの納戸に割り振り、会社に出勤するための目覚まし時計の使用を禁じ、平成23年には、原告が第二の人生に備えて海外留学したいという希望を一蹴するなど、原告に精神的虐待を加えた。
さらに、被告は、子らの教育方針に関する原告の意見を一切無視するほか、子らに対しては、頭が悪い等の暴言や暴力を繰り返していた。
そして、被告は、別居後は、原告の父である亡A(平成28年11月×日死亡)への電話を取り次がず、平成24年2月頃には玄関の鍵を増設して原告が自宅に入れないようにし、同年5月には原告の亡A宛ての手紙を同人に渡さずに原告と亡Aとの交流を妨害し、その間、原告に連絡なく亡Aと養子縁組するほか、亡Aの生命保険の受取人を原告から子らに変更し、亡Aの遺産についても原告やその姉に何も知らせないまま葬儀費用の支払を要求するなど、亡Aとの同居や婚姻関係継続の目的が金銭であることを明らかにした。
被告は、その他、亡Aから多額の贈与を受けていたにもかかわらず、婚姻費用の減額に一切応じず、原告の単身赴任手当を全額被告に引き渡すよう要求し、原告がスポーツジムの女性と不貞行為をしているとの妄想を抱いて同ジムに電話したり、原告の居住先を訪問して郵便物や写真を投函するほか、早朝深夜問わずに原告の携帯電話に何度も架電し、原告の勤務先のメールアドレスにメールを送信したり、勤務先に原告の連絡先を問い合わせるなどして原告の社内での立場を悪化させ、原告の心情や立場を全く理解せず、自らの感情の赴くままに執拗に原告に付きまとっており、前件訴訟において、原告の訴えを目の当たりにしても、自らの言動を正当化するばかりで、夫婦関係修復に向けた一切の努力をしていない。
そして、原告は現在、婚姻継続の意思がなく、別居期間も7年と相当長期間にわたっているから、婚姻関係は完全に破綻し、婚姻を継続し難い重大な事由がある。
(被告の主張)
被告は家事をおろそかにはしていないし、一時的に玄関に物を置いたことはあったが整理整頓はしていたし、ごみ袋が倒れて家族の靴に触れたことはあったかもしれないが、敢えて原告の靴の上に置くことはなく、原告の着衣について色彩的に明るいと述べたり、白髪染めが素敵だと述べたことはあるが,誹謗中傷などしておらず、浪費大王などとも揶揄していない。
また、Dのマンションにおける部屋割りも、物理的な限界の中で原告の居住時間が少ないことを考慮したものであったし、近隣に配慮して原告のセットした目覚まし時計のスイッチを消したことはあるが、使用を禁止したことはないし、原告が海外で仕事することについても応援していた。
子育てについても、原告が被告と共同での子育てに困難を感じているとは感じられなかったし、被告が思春期の子らを心配して注意や叱責することはあっても、原告は被告の子育てを評価していた。
そして、被告は、玄関ドアにデジタルロックを取り付けたことはあったが、平成24年2月20日付けのメールにより暗証番号を原告に伝えているし、被告が原告と亡Aとの交流を妨害したなどの根拠はなく、原告は、亡Aの面倒を被告に任せきりにしたことを正当化しようとしているにすぎない。亡Aとの養子縁組は、亡Aが被告に墓を守ってほしいとの思いで行ったものであるし、生命保険の受取人変更も、亡Aが身勝手な原告の姿を見て、子らが可哀想だとして行ったものである。
加えて、被告が高額な婚姻費用の支払を求めたことはなく、今までどおりの生活費の支払を求めたにすぎず、原告の勤務先に原告の連絡先を問合せたことは一切ない。
上記のとおり、原告の主張する事柄は全て的外れであるし、原告は、前件訴訟の提起について被告に謝罪しており、被告は、再び原告と同居して誠実に関係修復をしたいと考えているから、婚姻関係は破綻しておらず、婚姻を継続し難い重大な事由はない。
(2)争点(2)(親権者の指定)について
(原告の主張)
二女は、被告から暴言や暴力を受けており、原告との別居後は、被告から不貞行為の証拠集めを命じられるなど、異様な母子関係に陥っているため、親権者は原告が相当であるが、二女の意向を尊重する。
(被告の主張)
争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実、証拠及び各項末尾に掲記した証拠等(枝番含む)《略》によれば、次の事実が認められる。
(1)原告と被告は、知人の紹介で知り合い、平成5年8月×日、婚姻の届出をし、原告が会社員として稼働し、被告が専業主婦として家事・育児に従事し、平成19年頃には、被告及び子らが原告の赴任先であるシンガポールに赴いて同居していたところ、栃木県内の原告の実家(以下「原告実家」という。)で一人暮らしをしていた亡Aが、高齢になるに従い、日常生活が困難になってきたため、被告及び子らが原告の赴任期間終了前に帰国して亡Aと同居することとして、3LDKのDのマンションを購入し、同年3月頃、被告と子らが帰国し、平成21年11月14日、亡Aと被告及び子らが同居を開始して、原告は一時帰国の際にDのマンションを訪れるなどしながら、おおむね円満に生活していた。
(2)原告は、平成22年9月、単身赴任を終えて帰国し、Dのマンションで家族5人での生活を開始したところ、次第に被告の言動が不快に感じられるようになり、平成23年5月頃、東京都足立区Eに5LDKのマンションを購入し(以下、このマンションを「Eのマンション」という。)、手狭であったDのマンションから転居した際にも、必要な物品を揃える中で、被告と意思疎通ができないと感じて被告に対する忌避感が生じ、平成23年6月11日、被告との同居が耐えがたくなり、離婚の意思があることを秘して、サマータイム期間中は勤務先近隣に居住する方が便利であるなどの虚偽の理由を告げ、東京都品川区のマンション(以下「Fのマンション」という。)に転居し、同年7月25日、電話で、被告に離婚したい旨告げたが、被告は、原告が離婚したいとする理由には根拠がないと考え、離婚には応じなかった。
(3)前件訴訟の第一審は、平成25年7月30日、棄却され、同年10月30日、原告の控訴も棄却されたが、その間、原告は、被告に知らせることなく、長崎、東京、宇都宮に順次転勤し、平成25年9月頃には、亡Aが原告の勤務先に電話したり、平成26年から平成27年にかけて、被告が前件訴訟の原告代理人宛てに、子らの現状などを伝える写真、図画及び手紙などを複数回送付しても応答しなかった。
被告は、同年5月頃、原告の勤務先の健康保険組合に連絡して原告の個人情報にアクセスし、配偶者の健康保険の案内の送付先を書き換える過程で原告の居住先を知り、同月9日、亡Aを伴って同所を訪れた。原告は、その晩、被告に何度も架電したが、被告はこれに応答しなかった。
被告は、その後も、原告の居住先に手紙を送付したり、持参するなどしたが、原告の離婚の意思は変わらなかった。
(4)亡Aは、Dのマンションに入居後、一貫して被告及び子らと同居し、月額10万円を生活費として被告に交付し、平成25年10月25日、被告を養子にし、その他、原告が受取人となっていた生命保険の受取人を子らに変更し、原告実家の売却代金を被告に贈与して、平成28年11月×日に死亡した。
原告は、被告からの連絡を拒絶していたこともあり、亡Aの死後、初めて被告と亡Aとの養子縁組、亡Aの生命保険の受取人変更及び原告実家の売却代金の被告への贈与の事実を知るほか、被告から葬儀費用の支払も求められ、被告への不信感が増した。
原告は、同年12月1日、Eのマンションを訪れた際、できることなら平和的に解決したいとして、前件訴訟により被告及び子らを傷つけたことを謝罪したが、離婚の意思は変わらなかった。一方、被告は、平成29年5月下旬から6月上旬にかけて、原告代理人宛てに、なぜ離婚訴訟を提起するのか理解できない、離婚訴訟を提起しないよう求める旨の書面を複数回送付した。
(5)現在、原告の離婚の意思は強固である一方、被告は、原告が離婚原因として挙げる言動等には根拠がないから改善のしようがなく、原告が被告に正直に話せば婚姻関係は改善するとして、離婚を拒んでいる。
二女は、現在、被告の下で生活しており、その生育に特段の問題は窺われない。
2 争点(1)(離婚原因の有無)について
(1)上記1のとおり、原告は、単身赴任を終えて被告と同居を開始すると、被告の言動に不快感を覚えるようになり、Eのマンションに転居後も、被告と意思疎通ができないと感じて被告への忌避感が生じ、平成23年6月11日には、被告と同居するのが耐えがたくなって別居を開始し(上記1(2))、別居後は一貫して被告との離婚を求め、前件訴訟で敗訴しても離婚の意思は変わらず(同(3))、夫婦関係の改善が図られることのないまま、平成28年11月×日に亡Aが死亡すると、被告が原告の了承を得ることなく亡Aと養子縁組をしていたことや、亡Aの生命保険の受取人が原告から子らに変更され、原告実家の売却代金も被告に贈与されていたことなどを知り、被告から葬儀費用の支払も求められたことも加わり、被告への不信感が増し(同(4))、現在でも離婚の意思は強固である(同(5))。
(2)この点、確かに、原告が婚姻を継続できない理由として主張する被告の所作や発言等については、それ自体、婚姻関係を破綻させるだけの決定的な出来事であるとまではいえないが、被告が、亡Aとの養子縁組や、原告が受取人となっていた亡Aの生命保険の受取人変更、原告実家の売却代金の受領など(前記1(4))、原告にとって、身分関係上も財産関係上も重要な事項について、原告の理解を求めずに行ったことは、原告の被告に対する信頼を失わせるのに十分な出来事であるというべきであるし、被告が、原告が被告からの直接の連絡を拒む姿勢を示しているにもかかわらず(同(3))、原告の勤務先の健康保険組合に連絡して原告の個人情報にアクセスしてその内容を書き換え、その過程で知った原告の居住先を訪れるなどした行為(同(4))は、被告にとっていかに原告の行動が不当であったとしても、原告の心情や立場を理解しないものといわざるを得ず、これによって原告の離婚の意思が強固となったとしても、致し方ないというべきである。
そして、原告と被告との別居期間は、当審の口頭弁論終結時までに6年10か月が経過していること、現在も原告の離婚の意思は強固であること、被告は、少なくとも前件訴訟において、原告が婚姻を継続できないと考える原因について知り得たのであるから、一旦は原告の訴えに耳を傾けて歩み寄る姿勢を示すことも可能であったと思われるのに、原告が離婚訴訟を提起する理由が分からないとの態度を変えていないこと(同(4)、(5))に照らすと、いくら被告に復縁の意思があるといっても、婚姻関係は破綻し、その修復は極めて困難であるといわざるを得ないから、婚姻を継続し難い重大な事由が認められる。
(3)なお、被告は、本件訴訟が不当訴訟に当たると再三供述等するため、原告が有責配偶者に該当し、原告の離婚請求が許されないか否かについて念のため検討すると、確かに、原告が、被告に対し、離婚の意思を秘して別居を開始し、亡Aの世話を被告に任せきりにした点については、家族に対する責任を充分に果たしていないという面は否定できないが、日常の些細な言動が積み重なって忌避感が醸成され、これが同居困難なまでに高まることは十分あり得るのであって、原告が被告に対する忌避感を有するに至ったことについて原告に非があるとまでは評価できないこと、被告は、原告のこのような心情を一旦は受け止めるという姿勢を示していないことに照らすと、原告が婚姻継続の意思を失ったことについて、原告を有責配偶者であるということはできない。
また、被告が供述するように、Fのマンションの原告の部屋に女性のものと思われる髪の毛があり、被告が土曜日の午前中に原告の居住先の呼び鈴を押したが応答がなく、原告が女性とゴルフに行ったなどの事情が認められたとしても、これらをもって、原告が不貞行為を行っていたとは認めるに足らず、この点でも、原告が有責配偶者であるということはできない。
よって、原告の離婚請求が信義則上許されないということはできない。
3 争点(2)(親権者の指定)について
上記1(7)のとおり、被告による二女の監護の現状に特段指摘すべき問題があるということはできず、安定した監護の現状を変更すべき事情も見当たらないことなどからすると、子の福祉の観点から、二女の親権者を被告と指定するのが相当である。
4 結論
よって、原告の請求は一部理由があるから認容することとし、その余は理由がないから棄却することとして、参与員の意見も聴いた上で、主文のとおり判決する。
(裁判官 村松多香子)