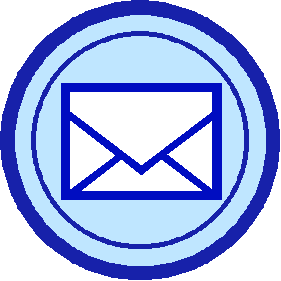婚姻費用算定に生活保護費は収入ではないとした家裁審判紹介
○夫は生活保護を受けている妻に婚姻費用として、過去分221万円と今後月額13万円を支払えと命令されましたが、審判でも「申立人が、相手方から後日婚姻費用分担金額の支払を受ければ、生活保護法に基づき同額を返還することになる可能性がある」と述べているとおり、受領金は国に返還することになりますので、結局、夫は、国に返還を命じられたことになり、また、月額13万円の収入が確実になったとすれば、生活保護は取消になると思われます。
○生活保護費を収入と認めないと言うことは、本来夫が支払うべき婚姻費用を国が一時的に立て替えているとの建前と思われ、生活保護の考え方としては正しいと思われますが、生活保護について不勉強な私には、この考えが正しいかどうか全く自信がありません(^^;)。
*******************************************
主 文
1 相手方は、申立人に対し、221万円を支払え。
2 相手方は、申立人に対し、令和3年10月から当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまでの間、毎月末日限り、1か月当たり13万円を支払え。
3 手続費用は各自の負担とする。
理 由
第1 申立ての趣旨
相手方は、申立人に対し、令和2年3月23日から、婚姻費用分担金として、毎月相当額を支払え。
第2 当裁判所の判断
1 認定事実
本件記録によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)申立人と相手方は、平成19年10月22日に婚姻した夫婦であり、平成21年×月×日に長女(現在12歳)、平成23年×月×日に長男(現在10歳)、平成24年×月×日に二男(現在8歳。長男、長女と併せて「子ら」という。)をそれぞれもうけたが、申立人は、令和2年3月23日、子らを連れて自宅を出て別居に至った。
(2)申立人は、令和2年4月30日、さいたま家庭裁判所越谷支部において、婚姻費用分担調停の申立てを行ったが(同裁判所令和2年(家イ)第384号。以下「本件調停」という。),令和3年5月21日調停不成立となり、本件審判に移行した。なお、同裁判所において、当事者間の夫婦関係調整(離婚)調停事件(同裁判所令和2年(家イ)第397号)、面会交流調停事件(同裁判所令和2年(家イ)第898号ないし第900号)、子の監護者の指定及び子の引渡し調停事件(同裁判所令和2年(家イ)第901号ないし第906号)も係属している。
(3)申立人は、別居後、令和2年6月28日から生活保護を受給し、生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び医療扶助を受けている。また、申立人は、平成28年11月から障害者年金を受給しており、令和3年7月14日には、同年4月に遡って障害者等級2級、基本年金額78万0900円、子らのための加算額52万4300円、合計年金額130万5200円の支給決定を受けている。
申立人は、精神科に通院中のところ、症状が安定してきたと診断されたことや、子らの監護養育に要する時間等を考慮の上、自らの判断で、同年6月7日から週3日ないし4日、勤務時間1日当たり4時間の就労を開始し、4万3588円の収入を得たが、体調不良により継続できず、同年7月6日、退職した。申立人は、現段階では就労再開の見込みは立っていない。申立人は、今後も、生活保護と障害者年金の受給を継続せざるを得ないと考えている。申立人の通院のための医療費は、障害者年金の支給額からではなく、生活保護における医療扶助によっている。
(4)相手方は会社勤務であり、令和元年は576万4799円、令和2年は540万3276円の給与収入を得ている。相手方も、かねて障害者年金の支給を受けており、令和3年6月以降の支給年額は61万3683円である。相手方は、障害者年金受給の前提となった病状のため、継続して通院して投薬治療を受けており、年間6万円ほどの治療費を要している。
2 検討
(1)婚姻費用分担額については、義務者世帯及び権利者世帯が同居していると仮定して、義務者及び権利者の各基礎収入(総収入から税法等に基づく標準的な割合による公租公課並びに統計資料に基づいて推計された標準的な割合による職業費及び特別経費を控除して推計した額)の合計額を世帯収入とみなし、これを生活保護基準及び教育費に関する統計から導き出される標準的な生活費指数によって推計された権利者世帯及び義務者世帯の各生活費で按分して割り振られる権利者世帯の婚姻費用分担額から、権利者の基礎収入を控除して、義務者が分担すべき婚姻費用分担額を算定する標準算定方式によるのが相当である(司法研究報告書第70輯第2号「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」。以下、同方式による算定を「標準算定方式」という。)。
(2)そこで、各当事者の収入額を検討する。
まず、申立人の収入であるが、前記認定事実によれば、申立人の別居後の収入は、令和3年6月1か月分の就労収入を除くと生活保護費と障害者年金である。生活保護は、国が最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する目的で行われているものであり、原則として世帯を単位として行い、扶養義務者の扶養等に劣後して行われるものであるから、相手方が負担すべき婚姻費用分担額算定に当たって、申立人が受給している生活保護費を申立人の収入と評価することはできない。
申立人が現実には生活保護費をもって生計を維持していたとしても、これ故に相手方の負担義務が免除されるものではなく、上記判断は左右されない。申立人が、相手方から後日婚姻費用分担金額の支払を受ければ、生活保護法に基づき同額を返還することになる可能性があるにとどまる。
他方、障害者年金は、前記認定事実記載のとおり子らのための相当額の加算もあり、受給する申立人及び子らの生活保障の一部といえるから、申立人の収入と評価するのが相当である。ただし、障害者年金は職業費を要しない収入であり、標準算定方式の前提となった統計数値により、全収入における職業費の平均値である15%で割り戻すのが相当である。
そうすると、申立人の年収は、上記障害者年金130万5200円を給与収入と擬制すれば153万5529円(130万5200円÷0・85)(1円未満切捨て。以下同様)となる。申立人は、平成28年11月から障害者年金を受給していたということであるから、令和3年7月14日の支給決定以前についても同額をもって申立人の収入とみなすこととする。
なお、前記認定事実によれば、申立人は、障害者年金受給の前提となった症状が安定してきたと診断されたことから、同年6月から就労日数及び時間を控えめにして就労を開始してみたが、結局体調不良により1か月4万3588円の収入を得たのみで退職せざるを得なかったこと、今後の就労再開の見込みが立っていないことが認められ、これら事情からは、やがては申立人にパート就労収入程度を見込める時期が到来するとしても、現段階において、申立人が得ている障害者年金収入に加え別途就労収入を継続して得る蓋然性があるものとまで認めることは相当ではない。よって、申立人の収入は、上記のとおり障害者年金のみとし、就労収入は、同年6月の1か月分も含め考慮しないこととする。
(3)相手方の収入は、前記認定事実によれば、令和2年の給与収入が540万3276円であること、障害者年金収入の令和3年6月以降の支給額が年額61万3683円であることが認められる。相手方の障害者年金収入も申立人の障害者年金収入と同様に、必要としない職業費平均値15%を加算すべく割り戻すと72万1980円となる(61万3683円÷0・85)。そこで、相手方の収入は、給与収入612万5256円とする(540万3276円+72万1980円)。
(4)前記のとおり認定した申立人の給与収入153万5529円及び相手方の給与収入612万5256円を前提に標準算定方式における算定表[(表16)婚姻費用・子3人表(第1子、第2子及び第3子0~14歳)]に当てはめると、12万円ないし14万円の上限程度と算定される。前記認定事実によれば、申立人が、障害者年金受給の前提となった病状についての治療費を、障害者年金額からではなく生活保護における医療扶助によっているのに対し、相手方は、障害者年金受給の前提となった症状の治療のために年間6万円の通院治療費を要していることなどに鑑み、相手方が負担すべき額は月額13万円とする。
そして、その始期は、申立人が本件調停を申し立てた令和2年4月30日とするのが相当であるから、同年5月以降となり、相手方の未払の婚姻費用分担金額は、同月から令和3年9月までの17か月分221万円(13万円×17か月)となる。
3 以上により、相手方は、申立人に対し、婚姻費用分担金として、令和2年5月からの令和3年9月までの未払額221万円を直ちに、同年10月から当事者が離婚又は別居状態を解消するまでの間、月額13万円を毎月末日限り支払うべきである。
よって、主文のとおり審判する。(裁判官 江尻禎)