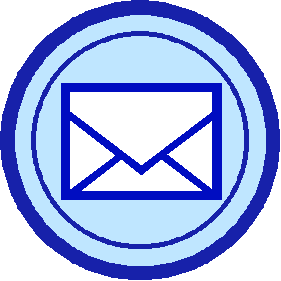内縁関係不成立として不貞行為損害賠償請求を棄却した地裁判決紹介
○事実関係を詳細に認定した相当長文の判決で、内縁の認定要件に関する部分が参考になりますので紹介します。
********************************************
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成26年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,被告と約4年間同居していた原告が,当時内縁関係にあった被告の不貞行為が原因となって内縁関係が破綻したと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年11月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提事実
(中略)
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(中略)
2 内縁の成否の判断基準
内縁とは,婚姻の届出をしていないため,法律上は夫婦と認められないが,事実上夫婦同然の生活をする男女関係のことをいい,内縁の成否は,当事者間に社会通念上の夫婦と認められる関係を形成する意思があるか(婚姻意思)と,社会的実体として夫婦同然の共同生活を営んでいるか(共同生活)の二つの要件の具備の有無によって判断すべきである。
このうち主観的要件である婚姻意思の存否は,当事者双方の主観的認識のほか,当事者の職業・年齢・経歴・社会的地位,結婚の慣習上の儀式の有無,共同生活の経緯・内容・生活状態,共同生活の継続期間,第三者の男女関係に対する認識等の外形的事情も総合考慮した上で判断すべきである。
(中略)
4 共同生活の有無の判断要素
(1)序論
内縁の成立のためには,当事者双方の婚姻意思と,共同生活の実態が備わることが必要であるところ,客観的な共同生活の態様は,婚姻意思の有無を判断するための外形的事情としても重要な意味を持つと考えられるので,初めに共同生活の実態に関連する事実関係を検討する。
本件の不法行為の成否との関係では,被告が訴外女性との性行為に及んだ平成26年10月頃の時点(以下,当該時点で被告が訴外女性との性行為に及んで相手を妊娠させた問題のことを「訴外女性問題」という。)で原被告間に内縁が成立していたか否かが焦点となるが,その判断には同月頃以降の共同生活の実態も影響を及ぼし得るので,事後的な事実関係も含めた上で検討を行う。
(中略)
5 婚姻意思の有無の判断要素
(1)序論
上記4で説示した共同生活の有無に関する判断要素は,婚姻意思の有無を判断するための外形的事情とも重なるので,共同生活の存在を支える客観的事実は,婚姻意思の存在を推認させる外形的事情としても機能するといえる。
一方,社会通念上の夫婦と認められる関係を形成する意思である婚姻意思は,婚姻届を提出していない当事者間に婚姻と同様の法的地位を付与する要件の一つであるから,婚約をした当事者間に共同生活の実態が存在する場合であっても,婚約が飽くまで将来において婚姻関係に入ろうとする男女間の合意であり,通常はある一定の時期に入籍をして夫婦としての法的地位を形成することを念頭に置いた上での意思の合致である以上,当事者の認識が未だ婚約の域を出ない場合と,これを超えて社会通念上の夫婦と認められる関係となることを共に希望する段階にまで達していた場合とは区別して考える必要がある。婚約をした当事者間における婚姻意思の存否は,一般に婚約の目的となることの多い入籍を果たした状態と実質的に同視してよいかという観点を踏まえて,入籍まではしていないものの,既に社会通念上の夫婦と認められる関係を形成する意思が当事者双方に確立されていたと客観的に認められるか否かによって判断すべきである。
このような問題意識を念頭に,上記4で説示した原被告間の共同生活の実態を支える外形的事情以外の婚姻意思の有無の認定上問題となる判断要素について検討する。
(中略)
(8)考察
前記(2)ないし(6)で掲げた事項は,(3)の前半で検討した本件マンションの単独所有名義の点を除き,いずれも原被告間における婚姻意思の認定上,消極方向に作用する判断要素となるものである。とりわけ二人の間で,本件マンションに転居する前月の段階から既に,今後二人が結婚に進むべきなのか,それとも男女関係を解消すべきなのかをめぐる真剣な話合いが始まっており,その後も1年近くにわたって,継続的に同様の腹を割った意見交換と衝突を繰り返していたという経緯(前記(4))は重要であり,この点は,前記4(6)において共同生活の実態の認定上特に重視した本件マンションへの転居と同居生活の継続に係る外形的事実(二人の結婚生活も念頭に置きつつ取得した本件マンションに転居し,その後訴外女性問題を挟んで約3年間本件マンションでの同居生活を継続していた経過)を基礎とした婚姻意思の存在の推認作用を明らかに弱める効果をもたらすものといわなければならない。
二人の間では,新居である本件マンションへの転居という文字どおり記念碑的な出来事を迎える前から,今後夫婦としての永続的な関係を形成する選択をして本当によいのかどうかを慎重に再考し始めていたところ,視点を変えれば,二人が平成24年12月に同居を開始してから,二人の間で結婚の可否に関する話題が顕在化するようになった平成25年10月までの同居生活期間は,せいぜい1年弱にとどまっており,新居への転居以外には,二人の関係の転機や深化を対外的に表明する特段の儀礼的行事や出来事もなかったのである(前記(2))。
以上に掲げた諸事情のほか,新居への転居の前後を通じて原告の母親への挨拶等の話が一切出ていなかった点(前記(2)),本件マンションに関係する保険金の受取人の名義が原告ではなく被告の母親になっている点(前記(3)),原告が主治医に対して被告の立場を必ずしも内縁の夫とは説明していなかった疑問が残る点(前記(5)),入籍をしない理由に関する原告の説明が曖昧で不自然である点(前記(6))は,全て婚姻意思との整合性に多かれ少なかれ疑問を生じさせる事項であることを踏まえると,前記4で説示した共同生活の実態に係る判断要素を考慮に入れたとしても,上述した平成24年12月から平成25年10月までの1年弱という比較的限られた期間内に,少なくとも被告の認識として,原告とは当初予定していた入籍はしていないけれども,既に原告との間で社会通念上の夫婦と認められる関係を形成する意思を確立していたとまで認定するのは躊躇われるところである。
また,本件マンションに転居前の被告の認識がこのようなものであった以上,その後の同年11月に本件マンションに転居してから訴外女性問題が発生した平成26年10月頃までの約1年間に,少なくとも被告の認識に大きな変化が生じて,原告とは当初予定していた入籍はしていないけれども,既に原告との間で社会通念上の夫婦と認められる関係を形成する意思を確立するようになっていたとまで認定するのもやはり躊躇されるといわざるを得ない。
もとより,主観的要件である婚姻意思の有無の判断は,共同生活の実態の認定根拠となる外形的事情を考慮に入れつつ行うのが相当であることは,前記2で説示したとおりである。他方で,将来遠からず入籍することを念頭に婚約をした当事者の少なくとも一方が,当事者間に婚姻意思があっても婚姻届を提出できない客観的な障害事由(婚姻に伴う改姓により不都合が生じるなど)があるわけではないにもかかわらず,自身も度々話題に出していた結婚に進むという選択を敢えて見送り続ける態度を示していたことは,当該一方の当事者において,婚姻を果たした夫婦の段階と,婚約者にとどまる段階とを明確に峻別した上で,入籍をするまでは夫婦としての法的地位の形成は欲しないという姿勢を表明したものと捉えるのが相当であり、このような場合に夫婦と同様の法律関係が形成されていたと認定するには慎重な考慮が必要である。前記4(2)の交際及び同居の経過を過度に重視できない状況であることは,既に述べたとおりであるが,その他の前記4(3)の同居期間中の対外的な振る舞いは,事実上の夫婦には至らない婚約者の立場であっても説明が可能なものといえる。
また,前記4(5)の訴外女性問題への対応状況も,少なくとも被告の認識において,原告との関係がどのようなものであれ,原告の紹介を通じて委任することとなったF弁護士の法的助言を得つつ,自身の身分上の問題につき適切な解決を図るべき必要に迫られていたことに変わりはなく,これに加えて,原告の鬱病等の問題に解決の道筋がつけば,将来原告と結婚する可能性もなお残されていたことからすれば,被告が訴外女性との交渉を進める過程で最大限原告の理解を得られるように努めて行動していたとしても不合理ではなく,必ずしも事実上の夫婦でなければ説明がつかないものではないといえる。
そうすると,前記4(6)で説示したとおり,原被告間には内縁を基礎付ける共同生活の実態が相当程度存在していたと評価できることを考慮に入れたとしても,前述した婚姻意思の認定を妨げる諸々の消極的な判断要素と併せて総合的に考察した場合に,平成26年10月頃の時点で,原告と被告の双方に確たる婚姻意思が存在していたとまでは認め難いといわざるを得ないから,結局,婚姻意思の要件の充足を認めるに足りる証拠はないというほかない。
6 争点(1)(内縁及び不法行為の成否)について
上記5(8)で説示したとおり,原被告間には,平成26年10月頃の時点で双方に婚姻意思が存在していたとは認め難く,内縁が成立していたとは認められない。そうである以上,被告が原告に対する貞操義務を負っていたとはいえず,被告が原告との同居期間中に訴外女性との性行為に及んだとしても,原告に対する貞操権侵害及び内縁関係破綻を理由とする不法行為は成立しない(なお,前記認定事実(12)の二人が同居生活の解消の合意に至った経緯に加え,通院先の診療録(乙6,7)には,被告の訴外女性問題とその後の対応経過が主たる原因となって被告との男女関係の終了を余儀なくされたことを窺わせる趣旨の記載は存在せず(二人の間のメッセージのやり取りにも,これに直接符合する記載は乏しい。甲29),むしろ,二人の関係が不可逆的に悪化した平成28年9月1日の直前の同年8月20日の診療録に「彼と価値観の違いで衝突する。理想の形をおしつけてくる。」との記載があること(乙6)に鑑みると,二人の関係が最終的に破綻した主要な原因が訴外女性問題にあったといえるのかは疑問を差し挟む余地がある。)。
7 結論
よって,本訴請求は理由がないので,これを棄却すべきである。東京地方裁判所民事第42部 裁判官 篠原敦